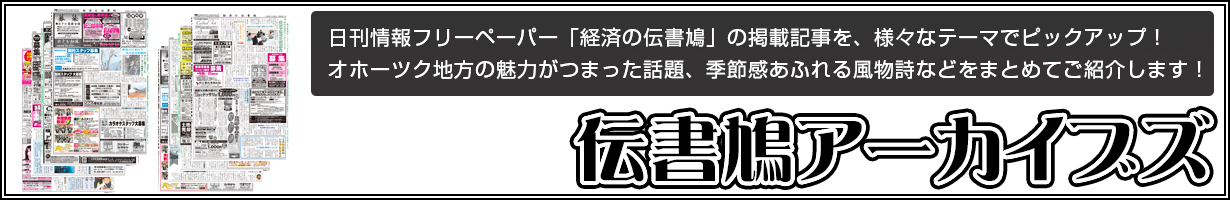
※各テーマの記事は最新のニュースから順に掲載しています。
テーマ:まちづくり
島根県海士町 財政危機から若者が集うまちへ ①
2025-07-09
社会
まちづくり~未来へつなぐ物語
少子化による学校の存廃は、オホーツク地域の自治体にとっても重い課題となっている。一方、同様の悩みを抱えていた島根県の海士町(あまちょう)は「島留学」や「島親制度」という独自の政策で高校の生徒数を増加させ、地域活性化と人口減少抑制につなげた。海士町の島留学制度の概要や成果、実際に島留学を活用した卒業生の声のほか、オフィシャルアンバサダー、半官半Xなど、ユニークな取り組みを紹介する。(3回連載予定)
地域、学校、行政が一体となり「島留学」「島親制度」などの取り組み

島根半島の沖合約60㌔に浮かぶ隠岐諸島の一つ、中ノ島に位置する、人口約2200人の町が海士町である。豊富な海産物だけでなく、米作りなど農業も盛んに行われている。
当時の町長、山内道雄さんは、2002年から経費削減をはじめ、自らの給与カットなど、大胆な財政再建に着手した。この動きは管理職らに伝わり、自ら給与カットを申し出た。さらに一般職にも広がり、05年度には「日本一給料の安い自治体」といわれるほどになった。
こうして捻出した費用を町の発展の原資とし、当時廃校の危機にあった地域唯一の高校、海士町の隠岐島前(どうぜん)高校の再建に着手。地域、学校、行政が一体となり、08年、「島留学」や「島親制度」などの取り組みを始めた。
◎島留学
「留学」という形で、島外からの進学者を募集。生徒が「通いたくなる」保護者が「行かせたくなる」そんな魅力的な高校を目指し学校の改革にも着手。首都圏などの講師による「遠隔授業」や、生徒たちの夢実現へ向けての「夢探求」や「夢ゼミ」などを取り入れた。
◎島親制度
島民たちが親代わりとなって、生徒たちを支える仕組み。入学前に生徒が興味のあるものをあらかじめ伝えると、それに応じて地域住民とのマッチングを図る。
◎公立塾
学力向上と居場所づくりを目指し開設。同高校と連携して学習支援やキャリア形成など、生徒たちの多様なニーズに対応している。
これらの取り組みにより、全国から生徒が集まっただけでなく、地元中学からの進学率も高まった(表①)。
さらに、人口増加や観光客の増加にもつながった(表②)。
こうした動きが広がる中で、地域住民と生徒との交流が活発になった。さらに22年より、週に1日、自分のやりたいプロジェクトに打ち込める「地域共創DAY」が導入され、地域住民と連携し、実践的に学んでいる。こうして地域住民とのつながりはさらに深まり、生徒自ら地域の課題を見つけ、地域住民と協力しながら解決を目指す取り組みを進めている。
地域の人たちからは「若い人が一人でも増えれば嬉しい。自分も若くなれる」などの声が寄せられた。また、島留学をしていた生徒が、進学などで一旦は海士町を離れたあと、再び戻ってくるケースも増えている。
次回は、東京から同校へ島留学し、卒業後は進学のため海士町をはなれたものの、「大人留学」という制度を活用し、現在は高校魅力化コーディネーターとして、海士町で活躍する、廣瀬惟來(ひろせいく)さん(20)を紹介する。 (知)
7月は「社会を明るくする運動」の強調月間
2025-07-03
社会
北見市では初日に街頭啓発

第75回「社会を明るくする運動」をアピールする街頭啓発が1日、北見市内の北見駅前広場とその周辺で行われた。
この運動は犯罪と非行の防止や立ち直りへの理解促進を目的とする全国的な取り組みで、7月が強調月間。
北見市では、辻直孝市長を実行委員長とする推進委員会が中心となり、運動を推進。この日は保護司会や防犯協会など関係する20団体から110人ほどが参加した。
辻委員長は「犯罪や非行のないまちづくりに向け、皆さんと一緒に取り組んでいきたい」とあいさつ。運動への参加を呼びかける内閣総理大臣のメッセージが、北見地区保護司会の永井求会長から辻委員長に伝達された。
続いて参加者が手分けして街頭啓発を行い、道行く市民にリーフレットなどを配布した。 (柏)
地元高校の存続に向け
2025-06-20
社会
網商の提言受け、協議会発足
年度内には意見まとめ

網走市教委は人口減少を見据え、市内高校を存続させるための検討協議会を立ち上げる。網走商工会議所からの提言を踏まえ、今年度当初予算に関連事業費を盛り込み、本格的な議論をスタートさせる。
今年度当初予算に盛り込まれた「魅力ある高校のあり方検討事業」(80万円)。目的は「地域に根ざした魅力ある高校のあり方について検討する」(市の資料より)となっている。
同市教委によると、検討協議会は近日中に設置される。メンバーは市内の経済業界や一次産業団体、地元高校、まちづくり関係者らで構成される見通し。
すでに、協議会の前身となる懇話会は立ち上がっており、昨年は5回の会合を開くなどして準備を進めてきた。
近日中に設置される協議会は今後、生徒確保などを視野に入れた魅力ある学校づくり策について意見を交わす。年度内には意見をまとめる方針だ。
網商は昨年6月、網走市内にある道立南ケ丘高校と桂陽高校の間口維持、存続に向けた提言書を、水谷洋一市長に提出。進む人口減少に伴い、地元高校の生徒確保はまちの重要課題と位置付け、「地域の発展には若い世代のエネルギーと新しい視点が必要不可欠」(提言書より)と危機感を募らせている。
道教委がHPで公開する、2025~2029年度の「公立高校配置計画案」資料には、網走市の中卒者数のデータが記されている。
2024(令和6)年の中卒者数は256人。27年までは260人前後で推移するものの、30年には176人に減少する。市内関係者によると、10年後の34年は「140人台を割込むというデータもある」。 (大)
連載 新庁舎完成後の行方~網走市~ ㊤
2025-06-19
社会
商店街の活性化目指し地元高校生の知恵募る
網走市役所の新庁舎が市街地に建設され、供用開始から3カ月以上が経過した。水谷洋一市長は〝新庁舎効果〟の一つとして、市街地にある商店街の活性化に期待し、今年度の新規事業に地元高校生との活性化研究事業を盛り込んだ。若者のアイデアは、沈滞ムード漂う商店街にひと筋の光を灯してくれるのだろうか―。 (大)
庁舎建設地選定の理由の一つ
研究事業を予算に盛り込む
桂陽高生の請願きっかけに動き出し
幅広いアイデアから実現可能な策探る
■新事業
水谷市長は、新庁舎のいくつかの建設候補地の中から、地元商店街アプト・フォー(南4条通り商店街)に隣接する場所を選んだ。理由の一つに「商店街の活性化」を挙げた。
新庁舎は今年2月25日に供用開始。市職員約350人が商店街そばにある庁舎に通うため、「通勤時間帯は、商店街を通る人は間違いなく増えたと感じる」(市職員)。
市は今年度当初予算に、新規事業「アプト・フォー活性化研究事業」を盛り込んだ(予算額60万円)。この事業の目的は、「桂陽高校生や関係団体とワークショップなどを通じて、『フリースペース』等の設置について研究・検討する」(市の資料より)としている。
■請願
地元高校生と一緒に商店街の活性化について考える試みは、網走桂陽高校の生徒が網走市議会に提出した請願がきっかけだった。
昨年12月、網走桂陽高校の生徒グループは、網走市議会・文教民生委員会に、商店街アプト・フォーにある空き店舗をフリースペースとして設置することを求める請願を提出。同委員会での審査を経て、採択された。
網走市議会において、地元高校生による請願は珍しく、新聞やテレビなどで報じられた。
市は地元高校生による請願を踏まえ、新規事業を通じて地元商店街の活性化策を探る狙いだ。桂陽高校のほか、網走南ケ丘高校にも声をかけており、幅広い若い世代のアイデアに耳を傾け、実現可能な活性化策を探る考え。
新規事業では今後、まちづくりなどを専門とするコンサルタントからのアドバイスなどを踏まえ、地元高校生と商店街の関係者らが意見交換などをする。
……………
地元高校生のアイデアが即座に商店街の活性化につながるかは不透明だ。しかし、地元の高校生がまちづくりに参加する経験は、郷土愛の醸成にもつながるはずだ。
今回の新規事業の予算規模は小さいが、地元商店街の関係者がどれだけ積極的に関わるかが〝カギ〟となりそうだ。
香り彩るまちづくり推進
2025-06-13
社会
北見の香りゃんせ公園でハーブ植栽

北見の市民団体「香り彩るまちづくり推進機構」によるハーブの植栽事業が1日、市内の香りゃんせ公園で行われた。会員やコミュニティーガーデン(市民花壇)の新規利用者ら約30人が参加し、花壇の手入れを行った。
同団体は市からガーデンの管理を受託し、ハーブを身近に感じてもらおうと、希望する市民にガーデンを貸し出している。毎年、新規利用者や区画を拡大した市民にハーブ苗をプレゼントしており、今年は9組にバジルやナスタチウム、ジャーマンカモミールなどの苗35株を贈った。
植栽を前に、事務局長の井上俊彦さんは「おらがまち北見の魅力でもあるハーブガーデンの維持に協力を」とあいさつ。利用者達は夏の収穫を思い描きながら、花壇に苗を植えていった。 (理)
連載 辞めていく職員~網走市~ ㊤
2025-06-12
社会
〝人気の就職先〟だったはずが…
網走市役所の2024(令和6)年度の中途退職者は13人で、過去10年で最も多かった。本紙はこれまでも何度か〝辞めていく市職員〟について紹介してきた。人気の就職先だったはずの網走市役所。しかし、近年の中途退職者は増加傾向にある。 (大)
網走市役所の中途退職者・2024年度は13人
過去10年で88人20~30代が全体の7割

■88人
本紙はこれまでの取材から、2013(平成25)年度以降の〝中途退職者データ〟を保有している。今回の連載は、24年度を含めた過去10年に絞り、関連データを紹介する。
過去10年の中途退職者数で、最も多かったのは24年度の13人。次いで、15(平成27)年度と16(同28)年度の11人、23(令和5)年度9人などとなっている。
10年間で辞めた職員(中途退職者)は計88人で、年平均にすると9人となる。
データを踏まえても、24年度の中途退職者13人は突出している。こうした傾向は今後も続くのだろうか?。
■7割
過去10年の中途退職者を世代別で見てみると、20・30代は58人と最も多く、全体の7割を占めた。男女別では、男性6割、女性4割だった。
これまでに20・30代の中途退職率が最も多かったのは、17(平成29)年度の87%。次いで、18(同30)年度75%、15(同27)年度72%などとなっている。
将来の希望見えない、パワハラなど理由はさまざま
関連データからは、網走市役所を辞める職員は20・30代の若年層が多いことがわかる。
数年前に網走市役所を辞めた職員に取材したところ、「将来の希望が見い出せなかった」(男性)、「役所内の部署によると思うが、仕事を進める上でのダブルスタンダード(統一されていない基準)についていけなかった」(女性)、「上司からの厳しい指示(パワハラ)」(男性)などとの答えが返ってきた。
……………
網走において、市役所(職員)はまちづくりを進める上での〝主力エンジン〟である。若き職員はまちの未来で希望であるが、近年は役所を去ってしまうケースが目立つ。何らかの対策を講じることが求められている。
連載 人口減少による防犯灯問題~網走市~ ㊤
2025-06-05
社会
町内会への委託制度廃止防犯灯管理が市の直轄に
網走市内の各所に設置されている防犯灯の管理システムが変わる。来年度からは、すべての防犯灯管理が市の〝直轄〟となり、町内会の委託制度は廃止される。一方で、町内会が存在しないエリアへの設置が可能となる。委託制度を見直す背景には、人口減少に伴う「町内会の維持困難」などの現状があるようだ。 (大)
2523灯中684灯
人口減少で町内会の維持が困難に
町内会が存在しないエリアへの設置が可能に

■半分
防犯灯と道路照明(街路灯)は異なる。防犯灯は夜間、人通りの少ない住宅街などにおいて犯罪を防止することが目的で、地域住民や町内会からの要望を受けて設置されるケースも少なくない。
現在、市内に設置される防犯灯は2523灯(2日時点)。このうちの684灯は、町内会が管理している。
管理する町内会は「球切れチェック」などの管理委託料として、電気料の半分相当を受け取る仕組みだ。
市によると、すべての防犯灯はLED化されており、1灯あたりの電気料は1カ月300円ほど。単純計算だが、管理を担う町内会への委託料は月150円ほどとなる。
■見直し
町内会に防犯灯管理を委託する現行の制度は、2018(平成30)年度に創設された。
網走市連合町内会によると、18年の町内会数は212(3月末時点)、町内会加入率(全世帯に占める町内会加入世帯の割合)は63%。24(令和6)年は199、加入率59%で、人口減少に伴い町内会の数は減少している(表参照)。
同町連によると、2016(平成28)年度から24年までに17の町内会が解散した。新設された町内会は5つで、〝解散ペース〟が上回っている。
現行制度では、町内会の解散によって防犯灯の管理ができなくなった場合、その防犯灯は撤去することになっている。
ただ、町内会は解散したものの住民有志が管理を引き継ぐことも可能としており、市によると、現在は5つの住民有志が防犯灯の管理団体となっている。
人口減少に伴い、網走市では町内会の〝まちづくりの役割〟が問われている。防犯灯の管理問題はその一例で、市は人口減少により浮上した各種課題を見据え、現行の管理委託制度の見直しに着手する方針を固めたようだ。
TNR活動で野良猫の繁殖抑制
2025-06-05
社会
置戸おたすけニャンコ隊発足から1年
飼い主のいない猫の繁殖を抑える活動を行う置戸の町民グループ「置戸おたすけニャンコ隊」が発足し、1年が経過した。野良猫を捕獲し、不妊去勢手術を行った後、地域に戻す活動(TNR活動)を軸に、この1年で56匹を捕獲し、繁殖抑制に力を注いできた。代表の柳橋智春(ちはる)さんは「今後も地域全体に活動への理解を広めながら人と猫が共生できるまちづくりに貢献したい」と話す。
地域の環境衛生問題ととらえ捕獲して不妊去勢、地道に
柳橋さんは数年前、町内で猫の殺処分ゼロを目指す「NPO法人ニャン友ねっとわーく」の代表による講演会を主管団体の一員として企画した。講演を通じ、野良猫を地域の環境衛生問題ととらえる意識が広がったように思えたという。
柳橋さん自身も「増え続ける野良猫をどうにかしたい」と個人でTNR活動を始め、同じ思いを抱く仲間とともに昨春、同グループを発足させた。
猫は年2~4回発情期が訪れる。交尾の刺激により排卵するためほぼ100%妊娠し、1度の出産で4~8匹の子猫を産む。環境省によると計算上、1匹のメス猫は3年後には2千匹以上に増えるという試算もあるほど繁殖力が高い。野良猫が増えると、ふん尿被害や繁殖期の不快な鳴き声など、住民生活に支障が出る場合もある。
ニャンコ隊は現在9人で活動。飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施すことで繁殖を抑え、自然淘汰(とうた)される中で野良猫の全体数を減らしていく活動を地道に続けている。捕獲後に子猫を出産してしまうケースもあり、そうした場合は子猫の里親探しも行っている。
昨年はメス猫を優先的に捕獲。56匹のうち、11匹は里親が見つかり、45匹を地域に戻した。中心部における野良猫の数は「確実に減っている」と手応えを語る柳橋さん。捕獲した猫は写真付きでリスト化することで、地域に戻した後も個体把握ができるようになり、新たな野良猫の発見にも気が付きやすくなったという。
町中心部での減少に手応え
周囲の理解・支援に感謝
町内の各行事で活動をPRしてきたことで、町民らからペット用品が寄贈されることも増えた。町も保護猫活動団体支援として不妊手術などの費用補助を開始し「活動を継続させるためにも、とてもありがたい」と感謝する。
今後は牛舎などで繁殖する野良猫に対するTNR活動の推進が課題で「丁寧に理解を求めながら活動の輪を広げていきたい」と話している。 (理)
北見地区、北見地域防犯協会が総会
2025-06-03
社会
住みよいまちづくりへ
功労者表彰も

北見地域防犯協会(北見市北見自治区)と北見地区防犯協会(北見市、訓子府町、置戸町)の総会がそれぞれ23日、北見市内のホテル黒部で開かれた。
両協会の片山隆文会長は「特殊詐欺はいつ被害に遭ってもおかしくない状況。安全安心なまちづくりへ会員の皆さんがけん引役となって」などとそれぞれ挨拶。関係機関・団体と連携し、住みよい地域社会を築く今年度事業計画などを決めた。
功労者表彰が行われ、団体のほか個人表彰を受けた北光防災会の日浦洋会長は「地域の皆さんの協力で犯罪は年々減ってきている。今後も青色警らなどに取り組みたい」と話した。被表彰者は次の通り(敬称略)。
【北見地域表彰】
▽個人=池田公人、宮下尚樹▽団体=北光光栄町内会、北光防災会
【北見地区表彰】
▽個人=日浦洋、山本均、斉藤剛(以上北見市)、工藤良二(訓子府町)
▽団体=幸町5丁目町内会、西分会防犯パトロール隊(以上北見市)
香りゃんせフェス今年も開催
2025-05-30
社会
北見「香り彩るまちづくり推進機構」が総会

香り彩るまちづくり推進機構(田村友朗会長)の定期総会が20日、北見市役所で開かれた。昨年度の事業報告や、今年度の事業計画の承認などを行った。
同機構はハッカの歴史を受け継ぎ、香りを意識した地域文化などの魅力を伝えることを目的として、1994(平成6)年に発足した。
昨年度の事業報告では、第26回香りゃんせフェスティバルに約700人の参加があった事などが報告された。
今年度の事業では、全国ハーブサミット連絡協議会への参画や、7月開催予定の第27回香りゃんせフェスティバルなどを承認した。
田村会長はあいさつで「北見市の財政面や環境の変化により、公園の状況も変化し解決すべき課題もあるが、ピンチをチャンスに変え、香りゃんせ公園から北見の文化や魅力を発信していきたい」と語った。 (知)
花いっぱいのまちづくり
2025-05-30
社会
置戸の境野地区で花壇整備

花いっぱいのまちづくりに取り組む置戸町ではこの時期、町内随所の花壇整備が進められている。24日には境野公民館前で地域住民ら20人が参加し、花の植栽作業が行われた。
置戸では1978年から「花いっぱい運動」が開始。毎年5月から6月上旬にかけて各自治会やボランティア、商工会などによって地域の花壇や沿道の植樹帯などが花で彩られる。
境野地区では、公民館と自治連合会が中心となってマリーゴールドやベゴニア、サルビアなど約1400株の花苗を植えた。 (理)
桜とツツジ、成長願い
2025-05-28
社会
北見で市民植樹祭
花の種まき教室も

北見市の第85回市民植樹祭(緑と花の市民の会主催)が18日、市民スケートリンクに隣接する光葉町の市有地で開かれた。
緑と花があふれるまちづくりに向けて行われる恒例事業。この日は企業や団体、一般市民など合わせて220人ほどが参加し、エゾヤマザクラとヨドガワツツジ合わせて100本を手分けして植樹した。
このほか花や緑を育てる緑育の一環としてツツジの掘り取り体験や花の種まき教室を実施。初開催の花の種まき教室は10数人が参加し、フレンチマリーゴールド、キバナコスモスのどちらかを選んでプランターにまき、成長を楽しみにしながら持ち帰った。
危険な蜂駆除…自分たちの手で
2025-05-27
社会
北見の「上ところさくら会」がスズメバチトラップ作り講習会
市の駆除業務廃止で「日ごろから点検を」
スズメバチの巣作りが本格化するのを前に、北見市内の上ところコミュニティプラザで17日、スズメバチトラップ作り講習会が開かれた。地域住民23人が参加し、市環境課の職員から捕獲器の作り方と設置場所のポイントなどを学んだ。
上ところ地域住民協働組織「上ところさくら会」主催。財政健全化計画で今年度から市による蜂駆除業務が廃止となったことから、安全安心のまちづくり活動の一環として企画した。
参加者は2㍑サイズのペットボトルの上部に2㌢大の穴を3カ所開け、日本酒・酢・砂糖を混ぜた誘因液を注いで仕上げた。
市職員は、トラップは巣作りを始める女王バチの捕獲が主な目的で、5~7月に設置するのが有効と説明。それ以降は、多くのハチを呼び寄せてしまうため撤去し、設置場所は人がよく通る場所や子どもが手に届く高さを避けるよう話した。スズメバチが巣を作りやすい軒下や物置、庭木など「日ごろから住宅周りの点検をしましょう」と注意を呼び掛けた。 (理)
コンパクトなまちづくりへ
2025-05-23
社会
中心部への居住促進目指す
美幌町は、郊外型店舗が出店している青山北と稲美の両地区の国道243号沿いのうち、北側の都市計画用途地域を変更し、より大きな店舗が出店しやすくする。また、準防火地域の新町や仲町、大通など中心部の住宅地は指定を解除。住宅建築の条件が緩和されることで、建て替えや、中心部への居住を促し、コンパクトなまちづくりにつなげる狙いだ。
美幌町が都市計画用途地域変更準防火地域の指定を一部解除
青山北と稲美の国道沿いに大型店が出店しやすく
青山北と稲美の国道沿いに大型店が出店しやすく
青山北と稲美の国道沿いは、町のコンパクトなまちづくり計画で「沿道サービス拠点」に位置付けられている。
現在、道路の中心から南北それぞれ60㍍のエリアが帯状に、第二種住居地域に指定されている。店舗の誘致を図ってきたが、近年は各企業の店舗が大型化していることもあり、現行の奥行きでは追従できなくなっていた。
南側は住居地域に沿ってすでに住宅街が形成されているため、北側のみを変更する。道路中心からの距離を60㍍から100㍍に伸ばすことで、北見市や網走市など近隣の郊外型店舗と同様の、奥行き150㍍規模の出店が可能になる。町は「企業が出店しやすい環境にすることで、進出を促し、にぎわいを創出したい」としている。
準防火地域解除で住宅建設コスト軽減
一方の準防火地域はコンパクトなまちづくり計画の「中心拠点」「駅前交流拠点」に当たるエリア。現在、新町、仲町、大通など国道240号沿いを中心に合計71・2㌶が指定されている。
準防火地域では、火災が延焼しないよう、玄関ドアを鉄製にしたり、一部のガラスを網入りにするなどの対策が求められている。
町によると、これらの対策には、一般的な住宅で100万円以上がかかる。町が行った調査では、準防火地域は、その他の地域に比べて改築が進んでいないという結果が出ており、町は「対策のコストが建て替えを鈍らせている可能性があります」とみる。
今回の変更では、延焼の可能性が低いと評価された、商店が並ぶ国道沿いなどを除く35・9㌶の指定を解除。準防火地域は半分以下の35・3㌶とする。
道との協議経て6月に決定
2031年に開校が見込まれる義務教育学校整備候補地の美幌小学校が近いエリアでもある。町は「『学校の近くに家を建てたい』という希望が増えることが予想されます。中心部の建て替えが、コンパクトなまちづくりにつながれば」としている。
2つの変更はこれまで、美幌町都市計画審議会で審議され、了承されており、今後、北海道との協議を経て6月に決定する見通し。 (浩)
まちづくりパワー支援補助
2025-05-20
社会
新規3含む12事業を採択
北見市4自治区の対象事業決まる
北見市の2025年度まちづくりパワー支援補助金の審査結果が公表された。今年度は新規3事業を含む12事業を採択。事業名、主催団体、採択年数、補助金交付内示額は次の通り。
【北見自治区】
▽正調よさこい鳴子踊り振興事業(北見正調よさこい振興会)3年目、68万8千円
▽花壇整備とイベントによる来園者拡大事業(フラパラ市民の会)2年目、20万円
▽こども食堂高栄(こども食堂高栄)4年目、53万8千円
▽きたみホワイトイルミネーション(「がんばろう北見!」応援実行委員会)5年目、99万9千円
▽北見マラソン大会(北見マラソン実行委員会)新規、99万9千円
▽北見夜間中学の授業(北見夜間中学)4年目、57万6千円
【端野自治区】
▽地域猫活動(猫パトロールたんの)新規、40万7千円
【常呂自治区】
▽第3回北見オニオンカップカーリング大会(北見オニオンカップ実行委員会)新規、19万8千円
▽「打ち上げ花火で、共に!友に!」事業(常呂を明るくする実行委員会)4年目、94万5千円
【留辺蘂自治区】
▽おんねゆ森のコンサート(おんねゆ森のコンサート実行委員会)4年目、41万円
▽持続可能な町づくり事業(持続可能な町づくりの会)2年目、31万5千円
▽ほほえむ希望プロジェクト5(KITAMI LOCAL PROMOTION)5年目、55万円。
端野、常呂、留辺蘂自治区は予算に残額があるため追加募集を行う予定。
今年でラスト、春の園芸祭開催中
2025-05-16
行事
北見市緑のセンターで18日まで
17、18日にはハーブ普及展と盆栽・山野草春の展示会も
北見市緑のセンター前の特設会場で、北見園芸協会主催の「春の園芸祭」が開かれている。花苗や野菜苗、植木などを求める市民でにぎわっている。18日(日)午後3時まで。
園芸祭は1935年の樹苗即売会を起源とすると今年で90年に。同センターの廃止は来年度末だが、節目を区切りに園芸祭の開催は今年で最後とする。
会場には50~60種、大小1500鉢以上がずらり。販売担当の㈱田巻美石園によると、店頭にあまり出回らない8号鉢サイズの大きなバラ鉢苗をはじめ、色鮮やかな「ケイトウ」や「オステオスペルマム」など、定番ながらも管理しやすい品種を取りそろえたという。
野菜苗は昨年に続き、種なしピーマンや高糖度ミニトマトなどが人気だが「今年は生育が遅れ気味で数に限りがあります」とのこと。
このほか、17、18日には、香り彩るまちづくり推進機構の「ハーブ普及展」と、きたみ盆栽・山草同好会の「『盆栽・山野草』春の展示会」も同時開催される。 (理)
どうなる広域ごみ処理~大空町編~㊤
2025-05-15
社会
〝白紙撤回〟の東藻琴 候補地に含み
斜網地区1市5町(網走市、美幌町、大空町と斜里郡3町)の広域ごみの中間処理施設の建設地の候補地の一つに、大空町東藻琴地区が選ばれた。1市5町は当初、東藻琴地区に焼却施設を建設する予定だったが、産廃問題などで白紙撤回となった経緯がある。こうした〝特異〟な背景を持つ東藻琴地区がなぜ、再び候補地に挙がったのか? 先日の住民報告会では、賛成派と反対派の意見が寄せられた。 (大)
初の説明会に50人参加
反対、賛成派の考えは?
■4カ所
1市5町の広域協議会(会長、水谷洋一網走市長)は昨年12月、焼却施設の建設予定地について大空町から「取りやめたい」との申し出を受け、了承。建設地が白紙となったことで、新たな建設地の選定が急務となった。
同協議会は、新たな建設地の対象地を1市5町が所有する「1万4千平方㍍以上の開けた土地」と定め、各市町に提出を求めた。結果、13カ所の土地が提案された。
1市5町の副市町長6人と大学教授ら3人からなる第三者委員会(候補地評価委員会)は、13カ所の土地から「不適と考えられる」(活断層、埋蔵文化財など)7カ所の土地を除外。残った6カ所の土地については、所有するそれぞれの市町が絞り込み、結果的に4カ所の土地が候補地に選定された。
候補地4カ所の中に、前代未聞の事態としてマスコミに大きく取り上げられた大空町東藻琴地区が含まれていた。
■反対、賛成
4カ所の候補地は今後、第三者委による総合評価を経て、広域協議会が来年7月までに1カ所に絞り込む―という流れだ。
大空町は今月9日、東藻琴で報告会を開催。参加者は52人(本紙の集計)で、会場はほぼ満席の状態だった。松川一正町長も出席し、住民の質問に答えた。
反対派の主な意見を要約すると、「白紙撤回となったのに再び候補地に選定された不信感」「短期間での候補地選定」「住民との合意形成の担保」。
一方、賛成派は「建設されることに伴った経済効果」「将来のまちづくりに重要」だ。
…………………
1市5町の中間処理施設の建設地はまだ決定したわけではない。しかし、東藻琴地区での報告会では、反対意見が目立った。背景には、白紙撤回となったのに再び候補地に選定されたことに対する驚きと困惑があるようだ。
新任ですよろしく
2025-05-13
none
北見自治会連合会新会長髙橋 日出男さん(76)
1人の不幸も見逃さず
頑張る地域のサポートを
環境部部長など歴任、清掃活動などに尽力
町内会を次の世代に引き継いでいく手伝いを

北見市北見自治会連合会の新会長に選出された髙橋日出男さん(76)は「1人の不幸も見逃さない住みよいまちづくりが基本の基本と、三原忠前会長から教えられました。一生懸命頑張っている地域をサポートしていきたい」と思いを語る。
髙橋さんが自治連の活動に携わるようになったのは2011(平成23)年。転勤族で道内各地を回っていたが妻の実家の北見に居を構えたことから、単身赴任をしながらも地域の町内会長や役員を務めた。定年後、誘われて自治連の活動に参加。はじめは文化部、続いて環境部の副部長を経て、今年の3月まで環境部部長として活動。長年地域をはじめ常呂や道内の海浜でのごみ拾いを続けているほか、自治連ではペットの散歩のマナーに関するポスター制作など、環境問題に向き合ってきた。
町内会活動について「ごみステーションと防犯灯の維持管理も大事ですが、それだけではない」と話す。普段から住民同士がコミュニケーションをとっている町内会は「災害や避難行動をするとき避難名簿を作成していなくても声を掛け合うことで安否確認につながり、尊い命を守ることができる」と考える。また課題として、少子高齢化により解散する町内会が出てきただけでなく、退職年齢が上がったことで役員のなり手不足にもつながっているという。「どうやったら次の世代につなげていけるのか。ひとつひとつの課題の解決に向けて、お手伝いしていきたい」と話す。
同自治連は今年、創立50周年を迎えた。「行政の公助だけではできないことも、自治連を通じ町内会との共助の力をひとつにすることで大きな力に変わる。ここに住んで良かったと思える、安心安全で住みよい地域をみんなでつくっていきたい」と意欲をみせている。 (菊)
泳げ!こいのぼり
2025-04-29
社会
北見の地域協働まちづくり会議高栄小校区
「きずな」がまつの木公園に5月7日まで
5月5日の「こどもの日」に合わせ、北見の地域協働まちづくり会議高栄小校区「きずな」が、今年も市内高栄西町の高栄まつの木公園にこいのぼり15匹を揚げた。
こいのぼりを揚げる家庭が減っていることから、子ども達に空を泳ぐこいのぼりを近くで見てもらうとともに、子ども達の健康を祈ることが目的。2022年に地域に眠っているこいのぼりの提供を呼びかけて始まった。
同会のメンバーがこのほど、公園を横切るように約10㍍の高さに張ったワイヤーにカラフルなこいのぼりを取り付けた。
公園を訪れた子ども達は、空を泳ぐこいのぼりに手を伸ばすしぐさをするなどして、その姿を楽しんでいる。
こいのぼりは5月7日に撤去する予定。 (菊)

北見市に地域活性化起業人
2025-04-21
社会
田中秀明さん着任二地域居住促進へ
㈱ローヤル企画と市 派遣に関する協定
辻市長を表敬訪問 まちづくり貢献に意欲

北見市は、制作会社の株式会社ローヤル企画(本社東京都)と「地域活性化起業人」の派遣に関する協定を締結した。起業人として着任した同社の田中秀明さん(55)が14日、辻直孝市長を表敬訪問した。
地域活性化起業人は、3大都市圏に所在する企業の社員を地方自治体へ派遣する総務省の制度。地域の課題解決に向け、民間のノウハウや知見を生かして地域活性化を図る。北見市における起業人制度の活用は初めて。
田中さんは同社入社以前、こまき新産業振興センター(愛知県)で企業マッチングによる製品開発やクラウドファンディング、DX推進やIoT導入などビジネスコンサルタントに関する業務に従事した。田中さんは1カ月の半分以上、市商工観光部産業立地労政課に勤務し、企業や人材の誘致、都市と地方に住居を構える「二地域居住」の促進業務などに携わるという。
表敬には同社代表取締役社長の松浦睦桐氏も出席し、「東京でのネットワークといろいろな方々からのお力を頂き、北見の魅力をPRしたい」と挨拶。田中さんは、起業人として「関係人口の創出や新しいコンテンツの掘り起こしと開発などを通じ、まちづくりに貢献できれば」と意気込みを語った。 (理)
開基130年、節目の日にまちづくり会社設立を
2025-04-17
社会
訓子府で地域おこし協力隊と地域活性化起業人の活動報告会
地域活性化起業人の脇坂 真吏さん
「行政と民間の〝隙間〟を埋めたい」
訓子府町で活動する地域おこし協力隊と地域活性化起業人の活動報告会が9日、町公民館で行われた。地域活性化起業人として「まちづくり会社」設立プロデューサーを務める脇坂真吏さんがメインスピーカーとして登壇し、同社の設立について開基130年を迎える来年4月1日を目指していると述べた。
まちづくり会社の設立は伊田彰町長の公約の一つ。基幹産業である農業を中心とした町の魅力発掘や価値の向上につながる取り組みを通じ、持続可能なまちづくりを目指すもので、昨年5月に脇坂さんが着任した。
今年度は常駐の地域おこし協力隊3人と定期的に町を訪れる地域活性化起業人2人が新たに着任し、起業に向けた動きが具体化する。
今後のスケジュールについて脇坂さんは、10月ごろまでに事業計画をまとめ、12月ごろまでに創業計画を作成すると説明した。出資に関して「町民と関係性を持ち、前向きに意見をもらいたい」と町民出資枠も検討していると明かした。
また「行政と民間の両者の良いところと隙間を埋めることが我々のミッション」と語り、行政のような幅広い分野を横断的にカバーする「クロス」、町内外の個人・団体をつなぐ「ハブ」、既存の事業者や活動を支援する「サポート」を基本概念に事業化を推進。現時点では「農業・観光・教育」が事業の中心になると話した。
報告会ではこのほか昨年度着任の地域おこし協力隊3人が写真を交えて活動を報告。今回、地域活性化起業人2人の人材派遣に協力した石井食品株式会社の代表取締役社長、石井智康氏も特別登壇し、地域に根付いた同社の取り組みを紹介した。 (理)
農業振興や人材派遣など6項目
2025-04-17
社会・話題
訓子府町と千葉県・石井食品が包括連携協定締結
玉ねぎを軸に商品開発
同社の2人を派遣
持続可能なまちづくり目指し
石井社長「一緒に模索し、形にしていきたい」
訓子府町とミートボールなどの製造販売を行う石井食品株式会社(本社千葉県船橋市)は9日、包括連携協定を結んだ。日本屈指の生産量を誇る玉ねぎを軸とした商品開発や地域ブランディングなどを通じ、持続可能なまちづくりを目指す。
同社は、食の循環型ビジネスモデルを構築する一環として「地域と旬」をコンセプトに、独自の商品開発をはじめとする地域との連携に取り組んでいる。道内の自治体と連携協定を締結するのは初めて。
協定は、農業振興、地域ブランディング、人材派遣など6項目において連携を図る内容。人材派遣では地域活性化企業人制度を活用し、同社の谷克彦さんと青山香織さんが4月に着任した。2人は町のまちづくり会社設立に向けた取り組みの一環として商品開発や品質管理などに携わる。
同日、町役場で行われた締結式で、伊田彰町長は「これを一つの契機に、地方創生の実現に向けて一段と動き出し、町民とともに持続可能な新たなまちづくりに進んでいきたい」と述べた。石井智康社長は「我々がどんなことができるのかを一緒に模索し、何か形にしていきたい」と話した。 (理)
訓子府町の地域おこし協力隊に新顔
2025-04-08
社会
武田悟さんと鈴木祐也さんが着任
訓子府町の地域おこし協力隊に斜里町出身の武田悟さん(60)と北見市出身の鈴木祐也さん(45)の2人が1日、着任した。伊田彰町長から辞令が交付された。武田さんはコミュニティーサポーター、鈴木さんはまちづくり会社設立スタッフの任務にあたる。
武田さんは高校卒業後、北海道警に採用されて定年まで勤めた。2019年4月から22年3月までの3年間は訓子府駐在所に勤務しており、着任にあたり「やっと戻ってこられた感じ」と話した。今後は警察官時代の経験を生かし、地域の見守り活動などに携わりながらコミュニティ活動の支援にあたる。
鈴木さんは北見工業大学を卒業後、空調メーカーの保守点検などを行う会社に就職し、営業から関連会社との調整、修理までをワンストップで行っていた。26年の設立を見据えるまちづくり会社の方向性を定めるために各分野への聞き取りなどに取り組む。
辞令を受け取った武田さんは「子どもからお年寄りまでが集まれる居場所づくりに取り組みたい」、鈴木さんは「緊張していますが、自分に何ができるのかを考え、行動していきたい」と意気込みを語った。
この日は、まちづくり会社設立スタッフとして宮城県出身の杉山惠美さん(49)も着任予定だったが、体調不良のため欠席。さらに6月1日からは、大分県出身の井上亮さん(45)も同設立スタッフとして協力隊に加わることが決まっており、町の地域おこし協力隊は6月までに全7人となる。 (理)













