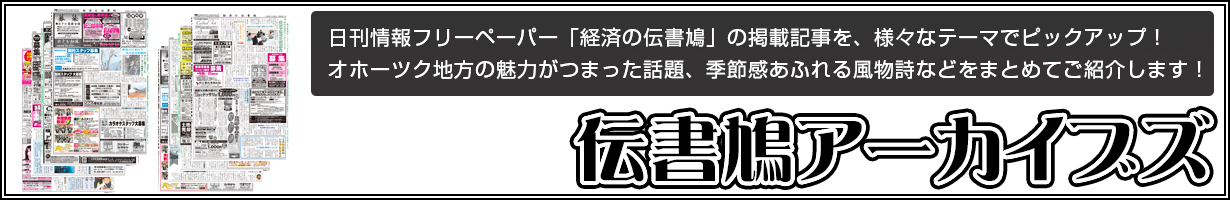
※各テーマの記事は最新のニュースから順に掲載しています。
テーマ:スポーツ
網走っ子は〝太め〟が多め?
2026-02-27
社会
「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
結果公表
網走市教委は、市内小学校5年生と中学2年生の男女を対象に実施した「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果を公表した。小5男子の「肥満傾向」、小5女子の「痩身傾向」などが全国・全道を上回った。
地域特有の環境が影響している可能性高く
調査は文部科学省の方針を受け、2008(平成20)年度から毎年実施。今回は小学5年生191人と中学2年生252人を対象に、昨年4月から7月末まで∧体格∨と∧実技∨などを調べた。
小5男子の「肥満傾向」は26%で、全国の約2倍だった。同市教委は「車社会の歩行不足、冬場の活動量低下、高カロリーな食生活など、地域特有の環境要因が複合的に影響している可能性が高い」(資料より)と分析している。
一方、小5女子は「痩身傾向」が6・9%で、全国・全道の2倍以上だった。同市教委は「現代社会における『痩せ願望』の低年齢化やスポーツ活動の影響も一部考えられるが、成長期におけるエネルギー不足は、将来的な骨粗しょう症や月経異常のリスクも高める」とした上で、「男子の肥満対策と同様に、適正体重の維持に関する指導が必要」(資料より)としている。
実技調査では、小5男女ともにソフトボール投げで全国平均値を上回ったものの、長座体前屈は下回る結果となり、「高い運動能力を持ちながら体が硬い傾向がみられる」(同市教委の資料より)。
氷の魔術師がアイスづくりを解説
2026-02-27
スポーツ
北見のアイスメーカー・奈良浩毅さん
ホールごとに個性があるほうが面白い

「カーリングホールのアイスメイク技術と競技への影響」をテーマに日本雪氷学会北海道支部などが開催した講演会。会場となったアルゴグラフィックス北見カーリングホールでアイスメーカーを務める奈良浩毅氏が難解な〝アイスづくり〟を分かりやすく解説した。
2020年のオープン当初は、ストーンの滑りが世界最速と言われた同ホール。氷の材料となる水は、自家製でろ過する北見の純水が他に比べ良質で滑りが良かったと振り返る。それも23年頃からは落着き、最近のトップ選手の意向もそうなってきているという。
タンクを背負い、氷上に水をまくぺブリングは、ホースの先のジョウロ状の部品が水しぶきの大きさを決める。最初にまくのは15度の水で片道50秒ほどかけて。2回目は40度のお湯を40秒ほどの速度でまいて仕上げる。
「お湯のほうが表面でゆっくりと凍り、水よりも平らな凸面になる」そう。さらにこの表面を削って、ぺブルの山の標高を揃える。「多く削ると曲がり幅が大きくなる。でも削り過ぎてもだめ」
滑りのスピードや曲がり具合など、競技者がなかなかアイスをつかみきれなかったり、逆にきっちりと読んで有利に利用する選手もいて、アイスメイクの醍醐味を感じる。
自身も競技者として公式戦に出場する。アイスを読みきる力が有利なのかと思いきや「難しい」と氷の魔術師にとっても奥深いようだ。「カーリングホールごとに違いがあるほうが面白い。アイスの違いを読みながら、試合観戦するのも楽しいですよ」と勧める。 (寒)
繊細な氷づくり、アイスメイクを深掘り
2026-02-27
スポーツ
北見工大など冬季スポーツ科学研究の一環

カーリング競技に欠かせない「アイスメイク(づくり)」について知ろうと15日、アルゴグラフィックス北見カーリングホールで講演会が開かれた。アイスの作り方によりストーンの曲がり具合が変わるという、アイスメーカーの興味深い話に耳を傾けた。
日本雪氷学会北海道支部が主催。アスリートの競技力向上を科学面からサポートする、北見工業大学冬季スポーツ科学研究推進センターが共催。同大学情報通信系の原田康浩准教授らが企画した。
講師を同ホールのアイスメーカー・奈良浩毅氏が務め、シート内の清掃、ストーンの拭き掃除など毎朝欠かさない準備から説明した。
奈良氏によると、まず前日のぺブルを8~9割削り取るイメージでスクレーパーという大きな機械を稼働。次いで氷上に凹凸をつけるぺブリングを行う。
水まきのぺブリングは2通りのやり方で往復。ホースの先の出口が小さくて細かな粒になるベース散布とやや大きな出口の仕上げ散布に分け、多彩な凹凸面を作る。せっかく作った粒だが、さらにニッパーで薄く削り、表面の高さを整える。
アイスづくりの最大の敵とされる結露対策について奈良氏は「室内を高めの気圧に保ち、外気が入り込まないよう特に夏の暑さ対策に苦労している」と述べ、空調機や純水製造機が配置されるバックヤードを案内した。

財政健全化でも削れない分野は死守を
2026-02-27
政治
吉田 哲氏が事務所開き
北見市議選2026
医療や介護・福祉、教育分野など

3月の北見市議選に立候補を予定する吉田哲氏(54)の後援会事務所開きが22日、大正住民センターで行われ、吉田氏の2期目挑戦へ支持者らが結束を固めた。
吉田氏は2022年の前回選挙で初当選。会派「次代」に所属し、総務教育常任委員会の副委員長を務める。
高齢者や障がい者などの社会福祉をはじめ教育、スポーツ振興などに力を注いでいる。事務所開きには船橋賢二道議会議員も駆けつけた。吉田氏は「財政健全化の中でも削ってはいけない医療、介護、福祉、教育の分野には特に目を光らせていきたい」と訴えた。
事務所は市西三輪3丁目752―66に開設。 (柏)
輪投げで広がる交流の輪
2026-02-20
行事
美幌町シニアクラブ連合会が大会開催
瑞治シニアクラブAが優勝

美幌町シニアクラブ連合会(平田美木男会長)の輪投げ大会が12日、スポーツセンターで開かれた。
健康増進や交流を目的に、年間2回開催。1チーム4人で、主にクラブ単位でつくる25チーム、100人が参加した。
それぞれ、3㍍先の的にめがけて9つの輪を投げる1ゲームを2ゲームずつ行い、チームの合計得点を競った。和やかな雰囲気の中でも、参加者はそれぞれ真剣な表情で的を見つめ、輪を投じていた。
山崎聡さん、鶴丸麗子さん、中嶋すみ江さん、前田栄治さんの「瑞治シニアクラブA」チームが167点で優勝。個人では、男性が63点を稼いだ前田さん、女性は62点を記録した報徳北シニアクラブの植村智代子さんが優勝した。 (浩)
各種大会結果
2026-02-20
スポーツ
none
◆第15回北海道ジュニアスキー技術選手権予選会北見会場結果
(8日、北見若松市民スキー場)
※決勝大会進出者(本紙エリア分)
【女子】
▽小学生
③菅原奏心(美幌ジュニアアルペン少年団)
④流水華那(北見北小6年)
⑤西若璃胡(北見北光小4年)
【男子】
▽小学生
①須貝耕一郎(北見ジュニアアルペンレーシング)
⑥山内一徹(同)
⑧木村奏太(北見三輪小4年)
⑨関凌雅(美幌東陽小6年)
▽ジュニアユース(中学生)
①芳賀奏太(美幌ジュニアアルペン少年団)
②関慧樹(オホーツクSジュニア)▽ユース(高校生)
①佐藤琉稀(北見ジュニアアルペンレーシング)
連載 フォルティウス個別インタビュー
2026-02-19
スポーツ
ミラノ・コルティナ冬季五輪
女子カーリング日本代表
オンライン会見より 吉村 紗也香選手②
チーム名は〝より強く〟 粘り強いチームに

―オリンピックをめざすようになったのは常呂高校の頃が原点でしょうか、思い出を教えてください
吉村紗也香選手「日本代表選考会の場に立ち、初めてオリンピックに挑戦できたのが高校時代でした。ジュニアの方に力を入れていて、そこまで意識はしていなかったのですが、それからは本気でオリンピックをめざす一つのポイントだったかなと。決定戦は1勝1敗の3戦までもつれ込んで、最後惜しいところまでいって、悔しかったという記憶があります。多分その頃に、めざしたい気持ちになり、今の自分につながっていると思います。貴重な経験でした」
―常呂で育ってこられて、常呂のカーリングの強さはどの辺でしょうか
吉村選手「女子でいうとずっと常呂出身の選手がオリンピックに出場していて誇りに思っています。そんな中で今回、常呂出身の選手が私を含め3人いて、出場できることが嬉しいです。本当にカーリングのまちなんだなと感じます。チームを離れても地元の人達が応援してくれて、本当に温かいまちだなあと。オリンピックの舞台を見てもらい、結果を出すことで競技の普及につなげていければ。常呂もだんだん人口が減ってきていますが、その中で頑張っている子もいますので、私も常呂出身の選手の一人として、子ども達に勇気や希望を与えられたらいいなと思います」
―フォルティウスという名前も存続の危機があったようですが、思い入れは
吉村選手「より強く!という意味なんですけれど、私自身この名前が本当に好きですし、新しくスタートするとなった時も、やっぱりこの名前でいきたいなという思いがありました。より強くなっていく姿をこの名前のもとで見守ってもらいたいと、この名前で再出発したいと他の選択肢はありませんでした」
―最後にその〝より強く〟について、フォルティスの一番の強さは何でしょうか
吉村選手「粘り強さだと思います。本当に粘り強いチームになってきたなあと思います」
―ありがとうございました <完>(寒)

応援背に白熱の攻防
2026-02-19
スポーツ
北見中央LC旗争奪ミニバス
北見中央ライオンズクラブ旗争奪ミニバスケットボール新人大会兼6年生大会が15日まで、北見と訓子府の会場で開かれ、選手達が熱戦を繰り広げた。
5年生以下の新人大会と6年生大会に分けて開催。新人大会は男子16チーム、女子12チーム、6年生大会は男子8チーム、女子8チームが出場した。
選手達は家族らの応援を背に、白熱の攻防を展開した。上位成績は次の通り。
【新人大会】
▽男子
①小泉・端野
②網走
③紋別
▽女子
①ポプラG
②美幌
③佐呂間・高栄
【6年生大会】
▽男子
①北見南
②小泉・端野
▽女子
①ポプラG
②美幌・小清水
北見市柔道協会が「親子転び方教室」
2026-02-19
スポーツ
安全な畳の上で思いっきり!
柔道の受け身やエクササイズ体験
〝礼の心〟も丁寧に指導
北見市柔道協会は11日、市武道館で未就学児と保護者を対象にした「親子転び方教室」を開いた。全日本柔道連盟の協力で東京から増田沙由美さん、灰原茉美さんを講師に招き、柔道の受け身や親子で楽しめるエクササイズを指導した。
市民の健康づくりや安全教育、柔道精神の普及を目的に開かれ、68人の親子が参加した。
準備運動は、曲に合わせて踊るなど工夫を凝らした内容で会場を盛り上げた。
続いて大外刈りや大内刈りの技を指導し、子どもたちは講師に技をかける体験をした。さらに、前や後ろに転んだ際の受け身の方法も学んだ。灰原さんは「柔道では相手を大切にする心が何より大事」と話し、礼の意味についても丁寧に説明した。
同協会の中澤伸一会長は、「冬の間、外で体を動かす機会が少ない子どもたちに、安全な畳の上で思い切り体を動かしてほしい。ケガをしないためにも、この機会に受け身を身に付けてもらえれば」と話した。
参加者からは「初めてでしたが、子どもがとても楽しそうで、いい体験になりました」との声が聞かれた。
この日はほかに、元オリンピック代表の山部佳苗さんを講師に招いた柔道教室やシニア向け転倒予防教室も行われた。 (知)




期待と不安…教え子の〝晴れ舞台〟見守る
2026-02-18
スポーツ
吉村選手所属チームの元・コーチ
常呂・小林 博文さん
中学校から大学まで家族のように
現役選手の目で成長実感「勝負師の顔に」

ミラノ・コルティナオリンピック女子カーリングの日本対スイス戦のパブリックビューイングが14日、アドヴィックス常呂カーリングホールで行われた。観覧席の最前列で応援する一人、小林博文さん(63、北見市常呂)はかつて、吉村紗也香選手(34)がスキップを務めたチームの元・コーチ。「地元の子だから」と中学2年のときに指導を任され、高校、大学と選手の入れ替えもなく約10年にわたり家族のように接してきた。「教え子なので」と親心のような不安な表情で見守った。
吉村さんが中学校の同級生とつくったチームwins(ウインズ)がコーチのスタート。4人が揃って常呂高校に進学すると「よし、えらい」と地元進学を喜び、変わらず常呂のホールで成長を支えた。
4人が札幌の同じ大学に進学すると「私が行ったほうがコストが掛からないので」と常呂から札幌のカーリングスタジアムへと車で通って指導した。チームは徐々に力をつけ、日本ジュニア選手権を3連覇。同世代の頂点へと昇りつめる。
34歳にしての吉村選手のオリンピック初出場については「もっと早く中学・高校生の頃に、一般の大会に出ていたら」と思い起こす。当時はチーム数が多く、ジュニア大会をはじめ道予選など一般の大会への道にも振り分けられた。同期のチーム常呂中学校は一般の大会の日本選手権へと駆け上った。
小林さんは今も現役選手を続け、試合の勘は鈍っていない。
オリンピックでの吉村さんについて「最初は緊張した表情だったけれど、スイス戦の中盤から本来の勝負師の顔になってきた」と見極める。遅咲きなので「これからだ」と闘将の眼差しで見守る。 (寒)
各種大会結果
2026-02-18
スポーツ
第58回美幌町冬季体育祭(町民スキー大会・クロスカントリースキー) 兼第11回美幌ロータリークラブ選手権大会結果
(11日、美幌町柏ヶ丘運動公園、1位のみ)
【男女混合】
▽幼児
①鎌田優花(大谷幼)
【男子】
▽中学
①桐山晴良(美幌中)
▽高校
①松本凌汰(美幌高)
▽一般
①吉田頼生(早稲田大)
【女子】
▽小2
①中川凜(美幌小)
▽小3
①晴山結衣(美幌小)
▽中学
①三浦有咲美(美幌中)
▽高校・一般
①石田正子(JR北海道)
▽一般
①畔上夢花(美幌町)
美幌町リリー山選手権大会
2026-02-18
スポーツ
子どもも大人も果敢な滑り
美幌町リリー山選手権大会兼美幌ライオンズ選手権大会(アルペンの部、美幌スキー連盟など主催)が11日、美幌町リリー山スキー場で開かれた。小学1年生から75歳まで、町内外から34人が出場。果敢な滑りを見せた。
競技は大回転。カーブでは雪煙を上げて旗門をくぐり抜ける迫力ある滑りを見せていた。
結果は次の通り(敬称略、1位のみ)。 (浩)
【男子】
▽小2
①中根龍希(訓子府小)
▽小3
①黒川永翔(同)
▽小4
①山本惟月(北見北光小)
▽小6
①髙崎啓(美幌東陽小)
▽中学
①芳賀奏太(美幌北中)
▽一般60歳以下
①石原秀人(北見市)
▽同61歳以上
①伊勢明(根室管内別海町)
【女子】
▽小1
①作田愛來(訓子府小)
▽小2
①奥谷優芽(網走小)
▽小3
①菅原奏心(美幌旭小)
▽小4
①奥谷有美(網走小)
▽小5
①中根希心(訓子府小)
▽小6
①藤本紗季(美幌東陽小)
▽中学
①藤原くるみ(網走第一中)
連載 フォルティウス個別インタビュー
2026-02-18
スポーツ
ミラノ・コルティナ冬季五輪
女子カーリング日本代表
オンライン会見より 吉村 紗也香選手①
必ずオリンピックに 悔しい経験が強い思いに
「メンバーがいたから」困難も乗り越え
成長を感じられていたから

―何度も何度も壁に跳ね返され、それでも今日まで続けてきた原動力は何ですか
吉村紗也香選手「挑戦する中で、どんどん成長していっている自分がいて、やっぱり目ざしたいという気持ちが自然と出てきて、積み重ねができての成長過程だからこそ、次は絶対行くみたいな。挫折とまではいかないけれど、悔しい思いは確かにしているんですけれど。次は絶対自分がオリンピックの舞台に立っているという強い思いにつながっています。競技性が新しくなったり、フィジカルの部分でもまだ成長できているという感覚があるからこその積み重ねで今まで来ているという感じです」
―チームの存続の危機や困難があった中で、どんな気持ちで活動を続けてきたのですか
吉村選手「悩んだ時期はありました。でも時間が経つにつれて、次こそはっていう思いになってきて。状況はゼロでしたけど、4人は揃っていました。苦しい時期もありましたけれど、みんなで支え合いながら乗り越えてこられた。辛かったけど、辛くはなかった。やっぱりメンバーがいたからかな。辞めようとはならなかった。代表決定戦で結果的に負けてしまったけれど、自分達の中ではすごく成長しているなと思えて、まだ自分達って強くなれるんじゃないかって、そういった兆しも見えて、まだ強くなれるんじゃないかっていう期待を持っていました」 <つづく>
全日本柔道連盟「形」強化選手に北見の4人
2026-02-18
スポーツ
東京での合宿に参加し腕磨く

北見の中澤佑紀さん、黒川俊光さん、中澤伸一さん、新海敬一さんが全日本柔道連盟の「形」強化選手に選ばれ、さきごろ東京都内で開かれた強化合宿に参加した。
同連盟は、全日本形競技大会の上位入賞者を中心に強化選手を指定。同大会6位の中澤佑紀さんと黒川さんのペアは、今後の育成・強化が期待される「指定組」、同大会5位の中澤伸一さんと新海さんのペアは世界大会上位を目指す「強化B」に選ばれた。
合宿では、形競技の技術向上や国際大会での活躍を目指して講習が行われた。
中澤伸一さんは「競技の奥深さと日本柔道の伝統を学び、さらなる技術力向上への大きな一歩になりました」と話している。
美幌グリーンロケッツが3連覇
2026-02-17
スポーツ
訓子府でオホーツク玉入れ選手権大会
初心者も競技体験
全日本玉入れ協会公認の「第22回オホーツク玉入れ選手権大会」が8日、訓子府町スポーツセンターで開かれた。訓子府や北見などから11チームが出場し、美幌町の「グリーンロケッツ」が大会3連覇を果たし、優勝した。
訓子府町教委とオホーツク玉入れ協会の主催。1チーム4~6人で編成し、100個の玉を高さ4㍍12㌢のポール上のかごに全て入れるまでの速さを競った。
訓子府高校の生徒が参加したほか、イカの仮装で出場するチームも見られ、大会を盛り上げた。今年は玉入れの楽しさを広く知ってもらおうとファンクラスの部を設け、玉入れ経験がほとんどない小学生や一般で構成する5チームも参加した。参加者たちは、2㍍50㌢のかごに50個の玉を投げ入れ、競技の楽しさに触れた。
惜しくも準優勝だった訓子府の「サックJAPAN」は、1次予選で15秒75の大会新記録を出し、ベストタイム賞を受賞した。
決勝の結果とタイムは次の通り。
①グリーンロケッツ(33秒80)
②サックJAPAN(43秒57)
③サックJAPANレディース(47秒83)
感動と勇気を!80歳以上のダンスチーム結成
2026-02-17
スポーツ
アクティブ80スマイルジャパンin北見
北見クラス「ルアーナ」で練習に汗
「ダンスを通して多くの人に感動と勇気を」と、80歳以上のダンスチーム「アクティブ80スマイルジャパンin北見」がこのほど結成。北見市光西町の北見クラスルアーナで練習に励んでいる。
NPO法人オホーツクウェルネス理事長で健康運動指導士の信清和志さんが、昨年行われた大阪・関西万博でステージに立った80歳以上のシニアダンスチームに感動。「同じ境遇にある多くの高齢者や市民に感動と勇気を与え、運動することの大切さを伝えたい」との熱い思いから、北見でのダンスチーム結成をめざした。
決起大会では見学・体験者含め15人が参加
夏ごろにイベントのステージ出演目指す
この日、練習初日となる決起大会には、見学や体験も含めた15人が参加。ダンスの指導などを担当するフィットネスインストラクターの竹岡美香さんは「一番は楽しむことが目的。人生の最高の思い出の1ページになってほしい。(見た人が)早く80代になりたいと思ってもらえるような楽しい時間を過ごしましょう」と呼びかけた。
さっそく竹岡さんのお手本とアップテンポな音楽のリズムに合わせてダンスに挑戦。不安な人は椅子に座ったままで手足を動かした。
参加者の中で最高齢の93歳の女性は「手足を動かしてとても楽しかった。これからもやってみたいです」と笑顔で話していた。
チームは、今後週1回の練習を重ね、今年夏ごろのイベントでのステージ出演をめざす予定。現在見学、体験も受け付けている。問い合わせは信清さん(0157-25-8284おこめ館)へ。 (菊)
スイスに勝った!
2026-02-17
スポーツ
カーリング女子日本代表を応援
3選手の出身・常呂でパブリックビューイング
ミラノ・コルティナオリンピック女子カーリングの日本代表チーム(フォルティウス)を応援しようと、選手3人の出身地の北見市常呂のカーリングホールで対スイス戦が行われる14日、パブリックビューイングが行われた。「大会の前半とは表情が違っている。これからだ」と応援にも熱が入った。
チームでは高校生まで常呂に住んでいた近江谷杏菜、小野寺佳歩、吉村紗也香の3選手が頑張っていて、ジュニアの時代から知る地元の人達らが足を運んだ。母親と訪れた小学3、4年の女子児童はカーリングを始めて1年。「選手達は上手。私もうまくなりたい」とテレビ画面を熱心に見入った。
ここまで0勝2敗の日本は、世界ランク2位の強豪スイスと対戦。試合の中盤以降、優勢になり7―5で勝利した。同じく常呂出身者らでつくるロコ・ソラーレの鈴木夕湖選手の両親も応援し「あのスイスに勝った」ともろ手を挙げて喜んだ。
吉村選手を中学から大学まで指導した元・コーチの小林博文さんも駆けつけ、教え子が活躍する様子を我が子のように見守った。
近江谷選手の父親で1998年長野オリンピック男子カーリング日本代表の好幸さんは「アイスをつかむのに苦労しているみたいだけど、対戦相手も同じ。これからだ」と気合を入れ直した。 (寒)
連載 フォルティウス個別インタビュー
2026-02-17
スポーツ
ミラノ・コルティナ冬季五輪
女子カーリング日本代表
オンライン会見より 小野寺 佳歩選手③
武器は、信じ合える力
常呂から継続出場すごい

―オリンピックで勝ち上がるために必要な要素は
小野寺佳歩選手「みんな金メダルを取りたいと思ってやっている。最終的にはやっぱりチームワーク。誰かが調子悪かったり、気持ちが不安だったりしてもそれを支え合えるチームの信じ合える力っていうのがオリンピックの舞台では重要になってくる気がします。私達は何度も勝たなかったら終わりという試合を経験して、それぞれの感情を共有し、何でも言い合える、そういうチームの力が試されるのかなと」
―常呂出身者がオリンピック8大会連続での出場です
小野寺選手「オリンピックに出続けるって純粋にすごいことだと思います。常呂の小1のおいっこがカーリング始めたので楽しみ。カーリングでオリンピックめざしたいという子どもが出てきてくれたらうれしいですね。スポーツに限らず興味のあることはいろいろ挑戦して、本当に自分がやりたいことは何なのかっていうのは、おとなになってから考えればいいと思います。まずは、自分が好きでやりたいことをつき詰めて、いろいろやってほしいなって思います」 (寒)
全日本スキー技術選 自分らしさ表現を
2026-02-16
スポーツ
北見市出身・出口 達稀さんロングターンに自信
いざっ全国へ

北見市出身のスキー競技者、出口達稀さん(北翔大学4年)が第36回全日本スキー技術選手権大会に出場する。不得手だった大回り種目が今回の道予選では高く評価され、新たな境地で大舞台に挑む。
ターンの美しさやスピード、バランスなど複数の視点から審査されるスキー競技。アルペンとの違いについて出口さんは「回転・大回転といった競技はタイムで明確に結果が表れるが、技術選はこれだという正解はなく、選手が個性を持ちながら競技できるところに魅力を感じる」という。
小学校から高校まで、北見若松市民スキー場でスキー少年団(北見JAR)で活動した出口さん。北見商業高校2年で北海道ジュニア技術選で優勝、高3で全日本ジュニア5位の好成績を収めている。
道予選は1日まで、後志管内ルスツリゾートスキー場で行われ、192人がエントリー。予選と決勝の計7種目による厳しい争いが繰り広げられた。
これまで小回り種目を得意としてきた出口さんだが、今回はロングターン(大回り)が予選、決勝ともに種目別5位。ごまかしのきかない基本の滑りが評価されて「大回りもやれるんだと嬉しかった」と自信をつかんだ様子。一方、こぶや荒れたバーンの不整地滑走は種目別28位。練習の機会の少なさを露呈した。
全国大会に進出できる、30位以内くらいを目標としていたが予選と決勝を合わせて14位。上には超一流選手だらけで、堂々と全国大会出場権を獲得した。
全国大会は3月秋田県で開催。全国からプロスキーヤーら200人を超す強豪が出場する。「50位以内をめざしたい。順位よりも自分らしさが表現できれば」と柔和な表情で意欲を語る。
束の間の帰省で8日、北見若松市民スキー場で行われた道ジュニア技術選北見予選会に顔を見せ、小中学・高校生選手らを前に競技の前走を務め、お手本の滑りを披露した(写真下)。 (寒)
連載 フォルティウス個別インタビュー
2026-02-16
スポーツ
ミラノ・コルティナ冬季五輪女子カーリング日本代表
オンライン会見より 小野寺 佳歩選手②
フィジカルとメンタル 学生時代の陸上経験生きる
バレエストレッチで体の安定感向上
家族に全力で競技楽しむ姿を見せたい
—チームでバレエストレッチを取り入れられているそうですが、体の変化は
小野寺選手「私はすごく体が硬くなりやすいので、柔らかくするように心がけています。パワーもつけつつです。ちょっとずつ年齢を重ねてはいるんですけど、まだまだ追い込めそうです。もともとパワー系で、筋力でねじ伏せるみたいな感じの動きがあったんですけど、それが自分が動きたいように動けるようになりました。デリバリーの安定性がすごく増してパフォーマンスも上がった感覚があって、自分としては本当に取り入れて正解だったなと感じますね」
—小・中学、高校、大学と陸上競技を併せてやってらっしゃいました。今、カーリングに生きていることは
小野寺選手「基本的なフィジカルのベースはもろにカーリングに生きています。今でも陸上競技のトレーニングを2、3継続し、取り入れてやっています。跳んだり、走ったり、投げたりというのは体の基本ですし、そこを幼い頃から強化できたのはカーリングに生かされているなと感じます。それとメンタル面でもピーキングの持っていき方とかは陸上と似てるのかなって」
—小野寺選手に対してはパワーとか筋肉とかいう話が多くなりがちですが、繊細なメンタルの持ち主だと常々思っています。先日のオリンピック枠獲得の大会では試合直後、父親の亮二さんも涙を流していました。涙もろいのは父親譲りですか
小野寺選手「オリンピック出場が決まった瞬間ですね。泣かせたというか、やっぱり喜んでほしいですね。かつて父にコーチしてもらったこともあるんですが、良い悪いはほとんど言いません。技術面が多いです。今回の決定戦では『素晴らしかったし、強かったよ』って言ってくれました。いろんな人に応援していただいているんですけれど、やっぱり家族が喜んでいる姿をみるのは幸せなものです。12年前は活躍している場を見せることができなかったので、今回は全力でカーリングを楽しんでいる姿を見せたいなと思っています」 <つづく>
たくさんの仲間と出会えた
2026-02-13
話題
北見歩くスキーの会井田正忠さん(87)に名誉検定員

北見歩くスキーの会の会長を務める井田正忠さん(87)が、全日本スキー連盟からクロスカントリースキーの「名誉検定員」と「功労指導員」に認定された。20年以上にわたる指導員歴を持ち、北見を中心にクロスカントリーの普及と後進の育成に尽力してきた功績が評価された。井田さんは「クロスカントリーのおかげで、たくさんの仲間と出会えた。ありがたい」と喜びを語る。
学生時代からテニスに打ち込んでいた井田さんは、定年退職後に冬でも楽しめるスポーツを始めたいと、55歳から歩くスキーを始めた。市の初心者講習に参加し「5年で選手に」と目標を立てて練習に打ち込んだという。
湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会には通算20回以上出場し、最長80㌔コースを走破。66歳と67歳の時には一般10㌔コースで優勝した。
身近に指導者がいなかったことから指導員を目指し、2002年に合格。上級者の滑りを参考にしながら検定員資格の取得に向けて努力を重ね、2年後の04年に検定員となった。以降、初心者教室や小学校などで競技の魅力を伝えてきた。19年からは同会会長を務め、若い世代の指導員や検定員の受験をサポートするなど、地域のスキー活動を長年支える存在となっている。
井田さんは、クロスカントリーの楽しみ方について「道具選びから雪原を滑り、山でおにぎりを味わうなど自然を体感できるのが魅力。上手な人の滑りを見て学ぶことやバッジテストを目標に練習したり、大会への出場をきっかけに、全国に友人ができることも醍醐味」と語る。今後も「無理のない範囲で楽しさを伝えていきたい」と話している。 (理)
自然感じ、さわやかな汗
2026-02-13
スポーツ
北見で歩くスキーの集い
小学生から一般まで60人参加
自然を感じながらそれぞれのペースで楽しむ「第30回歩くスキーの集いin北見」(実行委主催)が7日、北見市内のモイワスポーツワールドで開かれた。小学生から一般まで約60人が参加し、さわやかな汗を流した。
開会に先立ち、実行委の歩くスキーの会、井田正忠会長が「自然の中で汗をかき、大会で仲間と交流できる楽しみを感じてもらいたい」と挨拶。
当日は、風があったものの晴天に恵まれ、参加者はそれぞれの体力に合わせて、敷地内に設けられた起伏のある1周3㌔のコースを1〜3周し、景色を楽しみながら滑った。
また、全日本スキー連盟公認のクロスカントリースキーバッジテスト検定会も同時に開かれ、受験者が日ごろの練習の成果を試した。 (理)
連載 フォルティウス個別インタビュー
2026-02-13
スポーツ
ミラノ・コルティナ冬季五輪女子カーリング日本代表オンライン会見より 小野寺 佳歩選手①
常呂高では陸上もカーリングも
ロコはライバル、親友、仲間
—出身の常呂高校への今の想いは
小野寺佳歩選手「小さい高校ですけれども、そこでやっていた選手たちが一緒にオリンピックを目指し、出られるということに喜びを感じますし、素晴らしいことだと思います。学校の前に横断幕を飾っていただき応援してくださって嬉しいです。私の高校時代は勉強をやりつつ陸上競技もやり、カーリングもやってという割と自分の原点みたいな感じです。やりたいことをやらせてもらう中で、こうしてオリンピックに出られるということで、常呂高校を少しでも盛り上げられたらいいなと思います」
—これまでのオリンピックでの活躍もあって、日本ではロコ・ソラーレの印象が強い状況ではありますが、小野寺さんにとってはどんな存在ですか
小野寺選手「そうですね、本当に良きライバルであり、良き親友であり、本当に一緒に戦ってきた仲間だし、同じ年を重ねながらジュニアの時から今のところまでカーリング界を一緒に盛り上げられたすごく大切な存在です。でもやっぱりオリンピックとかの活躍を見ていると、自分達も負けてはいられないなという気持ちにさせてもらいました。彼女達がこんなに活躍できるのであれば、自分達もこれぐらい活躍できるんじゃないかという希望も与えてもらいましたし、本当にとても大切な存在ですね」
—昨年、オリンピック出場が決まった後、ロコから個別に声をかけられたりとかありましたか
小野寺選手「それこそ、ちな(吉田知那美選手)とかは9月の代表決定戦が終わった瞬間に『頑張ってね』って言ってくれましたし、ゆうみ(鈴木夕湖選手)は本当に明るくいつも通りLINEくれて『おめでとう頑張ってね』って。他のチームもみんなライバルではあるんですけど、それぞれが本当に素晴らしい人間性というか、これがカーリング精神なんだなとすごく感じました」 <つづく>
連載 フォルティウス個別インタビュー
2026-02-12
スポーツ
ミラノ・コルティナ冬季五輪
女子カーリング日本代表
オンライン会見より 近江谷 杏菜選手③
16年間変わらないこと「カーリングが楽しい」
楽しみながら世界の頂点目指し
地元・常呂の〝熱〟改めて実感

―吉村選手の投球のときにタッチし合うルーティンはいつ頃から
近江谷選手「吉村選手が産後に復帰した年からです。スキップというのは、常に考え込んでしまうポジションなので引きずらないように。白井一幸コーチから教わった『考える』ことと『戦う』ことのアクションの切り替えを大事にしています」
―リードの魅力は
近江谷選手「リードって常々、職人技だなって思っていて。同じようなことを繰り返しているようでいて、実は正確なショットの再現性が求められていて、下から支える役割を感じています。試合を作れるというのは、リードの醍醐味です」
―この16年間は長かったですか?16年間変わらないことは何ですか
近江谷選手「すごく短いです。あっという間に1年が過ぎます。変わらないのは…(少しだけ考えて)カーリングが楽しいっていうこと。人との出会いだったり、知らないことにふれたり、楽しみながらも世界のトップをめざすヒリヒリ感が日常生活にあるのが、ありがたいですね」
―前回16年前とオリンピック直前の気持ちに違いはありますか
近江谷選手「16年前はまったく想像できない世界に飛び込んでいくという、ちょっとフワフワとした地に足の着いてない気持ちだったと思います。今は、まさに決勝戦で戦うかもしれない相手とグランドスラムで試合していたり経験を積んで世界のトップレベルとどんな風に戦うのかイメージできているのがまったく違う点ですね」
―お正月に常呂に帰ったそうですが、中学・高校生の頃、チームgraceで戦っていた当時のことを思い返してどうですか
近江谷選手「北海道ジュニアで勝って喜んだなとか思い出します。オリンピックのことを口に出したことがあったかもしれませんが、こんなに時間が掛かるとは考えていなかったと思います」
―帰省して地元の人の声は聞かれましたか
近江谷選手「あらためて、すごく多くの方が実は毎回試合を観てくれていて『頑張ってー』とか『応援してるよ』とか今回は特に『オリンピック楽しみにしてるよ』って言葉にして伝えられたので、周りからパワーを送ってもらって私は勝てたんだなと意識できました」
―大切にしているというミーティングですが雰囲気は
近江谷選手「私も自分の意見を言いますし、うちのチームは皆一人ひとりが考えを持ってだれが率先してということもないし。意見が違うことがあったとしてもチームの中のルールとして、ゴールに向かって、金メダルを獲得するというゴールにつながる話をするというルールを決めているので、そのためだったら何でも言い合えるのがこれまで構築してきた中で一番いいところかなと思います」 (寒)
















