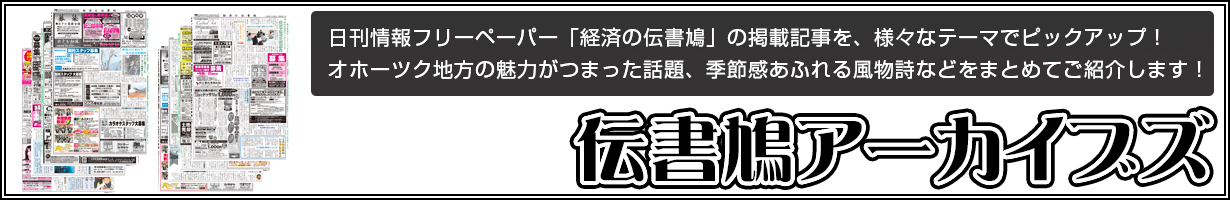
※各テーマの記事は最新のニュースから順に掲載しています。
テーマ:スポーツ
新任ですよろしく
2025-12-19
社会
美幌駐屯地司令・白鷹聖也さん(44)
任務を完遂でき、愛される駐屯地を

陸上自衛隊第6即応機動連隊長・美幌駐屯地司令として16日に着任した白鷹聖也さん(44)=1等陸佐=。「任務を完遂でき、地域に愛される駐屯地を目指したい」と抱負を述べる。
熊本県山都町出身。防衛大卒業後の2004(平成16)年に幹部候補生学校(前川原)に入り、第8師団司令部第3部長(北熊本)などを務めた。前職は陸上幕僚監部防衛部防衛課業務計画班長(市ヶ谷)。北海道の勤務は、第25普通科連隊第2中隊長(遠軽)を務めた14~16年以来2度目になる。「道東は寒いですが人が温かい。食事もおいしく、自然豊かで住みやすいところ。野菜や海産物が楽しみです」と印象を述べる。
隊員には「やるべきことを当たり前のごとく実行できる部隊」を求めた。「何をやるべきかを考えてやりこみ、強じんな部隊を目指したい」と話した。
趣味はランニングやスポーツ観戦。「来年のサッカーワールドカップが楽しみ。北海道に来たので、スキーもしっかりやりたいです」と話している。 (浩)
ボッチャで交流
2025-12-18
社会
美幌町シニアクラブ連合会
的めがけて楽しく

美幌町シニアクラブ連合会(平田美木男会長)のボッチャ大会が11日、スポーツセンターで開かれ、シニア世代が的をめがけて楽しくボールを投げた。
シニア世代の健康維持や交流などを目的に2023年から開催。過去2年間は体験会を兼ねた大会だったが、純粋な大会としては今回が初めてで、32クラブ96人と多くの人が出場した。
円形の的は中心から3点、2点、1点のゾーンがあり、1人2球ずつ投げて得点を競った。1チーム2ゲームずつを行い、村越レイ子さん、杉浦美子さん、名和妙子さんの「鳥里クラブB」が、34点で優勝した。
連合会はボッチャ、輪投げともに年間2回の大会を計画しており、2月には輪投げ、3月にはボッチャのそれぞれ2回目の大会を予定している。 (浩)
連載 フォルティウス より強く 遠回りの道ここから ⑭
2025-12-18
スポーツ
アウトターンのドローショット
互いに信頼のラストロック
「キター」想定通り
互いに2勝2敗の決定戦最終試合を前に9月14日、フォルティウスのメンバーは昼食をとりながらミーティングを行った。そこで最終試合の展開を想定し、選手達のイメージが一致した。
それは、最終試合の最終エンドの最終投球で、スキップの吉村紗也香選手のラストロック(最後の投球)で勝利が決まるという想定。難しい局面を吉村選手は「アウトターンのドローショットを決めきる」と想像し、大会では本当にその場面が訪れた。選手達は「キターキター」と高鳴る気持ちを抑えるのがやっとだったそう。
それでも「あとは吉村さんが決めてくれると信じていたので、自分達のやるべきことをやるだけ。意外と冷静でした」と小野寺佳歩選手。「吉村選手は4年前ここですごく悔しい思いをして、出産前よりも強くなって戻ってきた。メンタルもフィジカルも出産後そこまで落ちてなかったので、バージョンアップして帰ってきたなあという風に思いました」と人間性についても信頼を寄せる。
相手も素晴らしいドローを決め、止めるスペースは石1個ぶんほど。そんな状況でも吉村選手は吉村選手で「私は投げるだけ。手を離れたら後はスイーパーやコールがなんとかしてくれる」とやはり3人に信頼を寄せる。「大会まで4年間掛け、いい準備をしてきた。勝てるという自信があったし、絶対に勝つんだという強い気持ちをみんな持っていたので信じるだけでした」 <つづく>(寒)
西日本選抜学童軟式野球大会 道代表にセレクション
2025-12-18
スポーツ
北見の古里 優太くん
常盤クラブで磨いたセンスで
いざっ全国へ

北見市の古里優太くん(北見西小6年)が北海道選抜の小学生チームの一員として、第22回西日本選抜学童軟式野球大会に出場する。北海道チャンピオンシップ協会主催のセレクションで約5倍の狭き門を突破した。「チームの優勝へ、ヒットをたくさん打ちたい」と大張り切りだ。
同協会のセレクションが11月2日、千歳市のファイターズアカデミー専用球場で開かれ、道内各地から小学生98人が参加。キャッチボールと実戦形式の守備・打撃が審査された。
北見市内の野球少年団・常盤クラブで活動してきた古里くん。三振の取れるピッチャーや憧れの巨人軍・坂本勇人選手と同じ内野手として活躍。すでに卒団しているが主将を任され、チームの最大目標だった全日本学童軟式野球マクドナルド北北海道大会に導いた。
セレクションでは札幌や旭川の強豪チームの選手がたくさんいて「スピードは速いし、守備もうまかった」そう。それでも審査員を前にピッチングやサードの守備をミスなくこなし、結果を待った。千歳からの帰途、webで選抜メンバー19人が発表され「車内で、家族で喜び合った」そう。家族は「卒団後も長く応援できて幸せです」と感謝を語る。
選抜大会は全国から35チームを集め今月20日から岡山県倉敷市で開催。この1カ月間、週末はチームの合同練習や練習試合で札幌市や歌志内市などに遠征している。「いつも送迎してくれる親に感謝です」と古里くん。「みんなうまいけれど、自分もやっていけそうです」と前向きで、小学生の集大成として「一つでも多く試合したい」と楽しみにしている。 (寒)
若の里相撲大会で美幌・津別勢が健闘
2025-12-17
スポーツ
団体、個人で3位入賞
相撲王国北海道の復活に期待

美幌町相撲スポーツ少年団と津別相撲少年団の小中学生が6日、青森県弘前市で開かれた第3回若の里相撲大会に出場した。団体戦小学生高学年の部と個人戦小学生低学年の部でそれぞれ3位に入賞するなど活躍し、自信を深めた。
弘前市出身で、大相撲の元関脇として活躍した若の里さんの名を冠する大会。美幌から廣畑敬太くん(美幌小5年)、中武誠一郎くん(同6年)、永澤慶樹くん(同)、津別から増田翔大くん(津別小2年)、池田湊くん(津別中1年)が出場した。
美幌の3人が臨んだ団体戦は北海道、東北から13チームが出場した。美幌は予選リーグを3戦全勝で通過。決勝トーナメント初戦では八戸のチームを3―0で下したが、準決勝で田舎館のチームに1―2で敗れた。
大将の永澤くんは「みんなの頑張りで3位に入賞できてとてもうれしい。中学生になっても全国大会でみんなで入賞したいです」と話した。
個人戦には美幌の3人と増田翔大くん(津別小2年)、池田湊くん(津別中1年)が出場。このうち小学生低学年の部で増田くんが3回戦を勝ち抜いた。準決勝で惜しくも敗れたが「大きな大会で初めて3位になれてとてもうれしい。応援してくれた先輩たちのお陰です」と喜んだ。
5人を指導する白尾聡さん(42)は「子どもたちの努力が実を結び、とても良い内容でした。将来、大相撲を目指す子もおり、相撲王国北海道が復活したと言われるよう、今後も期待したい」と話した。 (浩)
フォルティウス・晴れ舞台切符
2025-12-12
スポーツ
カーリング女子日本代表
遅咲きチーム、本選予約
五輪世界最終予選を突破

北見市常呂出身の3選手を含む、カーリング女子日本代表チーム(フォルティウス)が念願のオリンピック切符をつかんだ。
8カ国によるミラノ・コルティナ冬季オリンピック女子カーリング最終予選。日本はノルウェーに丁寧な試合運びで6―5で勝利し、本選出場権を獲得した。
いずれも常呂出身の近江谷杏菜選手(36)は2010年バンクーバー大会以来16年ぶり、小野寺佳歩選手(34)は14年ソチ大会以来12年ぶりそれぞれ2度目の五輪出場となる。
同じく常呂出身の吉村紗也香選手(33)は初出場。高校生のときから5回目の挑戦で、大舞台を予約できた。大会前、長野五輪男子カーリングで日本代表スキップを務めた常呂の敦賀信人さん(48)は、同世代が常呂で高めあっていた中で「吉村さんは(オリンピックへ)行っていない。今回は行ってもらいたい」と話していた。
チームには常呂のカーリングのレジェンド、船山弓枝さんがコーチで帯同し、盟友の小笠原歩さんが日本カーリング協会から派遣されコーチに加わった。まさに常呂出身者により「総力戦で勝ち取った出場権」と吉村選手。「私達遅咲きだから」と自己表現する選手達に最終切符と満開に咲き誇る晴れ舞台が用意された。 (寒)
北海道代表として、いい走りを
2025-12-12
スポーツ
北見高栄中学校陸上部が駅伝で
いざっ全国へ

10月の全道中学駅伝で優勝した北見高栄中
北海道代表として、北見高栄中学校陸上部の男子長距離部が全国中学駅伝(14日・滋賀県野洲市)に出場する。
10月に新得町で開かれた北海道中学駅伝男子1部(6区間各3㌔)には35校が参加。
高栄中の1走は期待の支倉麻尋選手(2年)。「リズム良く走れた」とトップと14秒差の6位で2走の成ケ澤隼人選手(3年)へ。エースの成ケ澤選手は5人を抜く、区間賞でトップタイに上がる。
3走の萩谷大雅選手(同)、4走の谷澤星南選手(2年)も区間2~3位の好走でトップを守り、5走の加藤仁人選手(同)は「一旦前に出られたが、これを利用しついていく」作戦でラスト400㍍でスパート。最終・髙橋銀志選手(3年)は両足をテーピングして出走。「最後は足がつりそうでした」と気持ちのこもった走りで真っ先にゴールを駆け抜けた。ゴール後に「1年生のときは一番遅い選手でした」と目を潤ませ「創部2年目でここまでこられたのは監督の谷川亮太先生のおかげです」と感謝した。
チームキャプテンの成ケ澤選手は「つらい時こそ、みんなで励まし合って乗り越えてきた」と成長を語り、全国大会では「北海道代表としていい走りを」と意気込んだ。 (寒)
夜間や早朝にトラックが周回
2025-12-12
社会・スポーツ
北見市民スケートリンクで
散水作業が大詰め

北見市民スケートリンク(光葉町)では、400㍍ダブルトラックのリンクづくりが大詰めを迎えている。夜間や早朝の散水作業が連日続く。
リンクを管理する北見冬季スポーツ振興会は今月5日から散水作業を開始。しかし6日から8日にかけて暖気やみぞれ混じりの雨に見舞われ、作業を中断。気温が下がった10日に再開した。
大型のタンクを積んだトラックがコースをゆっくりと周回しながら、少しずつ氷に厚みをつけていく地道な作業。同振興会の工藤正俊理事長は「例年になく厳しい状況だが、何とか近日中にはオープンさせたい」と話している。
問い合わせは同リンク(0157-33-1280)へ。
メダルを手に凱旋
2025-12-11
スポーツ
北見柏悠会の選手が埼玉県の空手大会で活躍
篠木くんが優勝、池田さんが3位

北見空手教室柏悠会の篠木桃一くん(置戸小1年)と池田美寿々さん(北見南小4年)は、11月30日に埼玉県で開かれた第19回武蔵国空手道親睦大会で優勝、3位入賞と活躍した。
同大会は主に関東や東北、北海道、北信越の選手が参加するオープン大会で、柏悠会は初めて参戦した。
篠木くんは小学1年男子の部(形)に出場。予選リーグを勝ち上がり、決勝は2—1の判定で勝利を収めた。篠木くんは「上手に演武ができ、勝てて嬉しい。これからも練習してまた優勝したい」と話す。
池田さんは小学4年女子の部(組手)に出場し、3位に入賞。「悔しい。相手の動きをよく見ることができなかった。次の大会で1位を取りたい」と、好成績に満足することなく、さらに上を狙う。 (柏)
連載 フォルティウス より強く 遠回りの道ここから ⑬
2025-12-11
スポーツ
頼もしいスキップ 安心のスイーパー
互いに心強い信頼
「4年間掛けて積み上げてきたものが、しっかりと出せている大会だなあと感じていた」と吉村紗也香選手。「いい準備をして強い気持ちと自信を持ち続けることで勝利につながる。常にそれを思い出し、大丈夫だと自分に言い聞かせながら毎ショット投げていた」という。
スキップとして他の3選手を見て「緊張はあったと思うけれど、それを上回る集中力が伝わってきた」そう。「3人とも必ずいい結果が出る、と信じてプレーしてくれているから、私は投げるだけで良かった」と、安心だったと語る。
一方、小野寺佳歩選手は吉村選手について「コールはもちろん、チームが勝つための操縦をしてくれて、どんな局面でも決めてくれる。頼もしいスキップです」と、厚く信頼を寄せる。
吉村選手の投球前に毎回、互いの手と手を合わせるスイーパーの近江谷杏菜選手は「投球する人だけでなく、スイーパーやコールをする人もみんなが安心していつも通りショットに向かうことができるように。あとは、どんなときもにこやかに『よし、行こう』という気持ちを込めてタッチをしている」そう。
日本代表決定戦最終日。崖っぷちの状況で午前の試合を7—6で制し、対戦成績を2勝2敗としたフォルティウス。その日の午後に行われる大一番を前に、昼食をとりながらミーティングを行った。
「みんな切羽詰まった印象はなく、いつものフォルティウスでした」と小野寺佳歩選手。
選手達の覚悟とコーチ、スタッフそれにスポンサーやファンの気持ちが乗っかった究極の〝魂の投球〟が発揮される場面が、いよいよ訪れようとしていた。 <つづく>(寒)
連載 フォルティウス より強く 遠回りの道ここから ⑫
2025-12-09
スポーツ
前回敗退、一からのスタート
4年前の自分へ 諦めるな!と吉村選手

4年前の自分に何か言うとしたら、というインタビューに吉村紗也香選手は「実際のところ4年前に敗れた直後は、すぐにはまた次に向かうという答えは出なかったです。一からスタートするということで本当にたくさん、チーム内で話し合って、やっぱりオリンピックをめざしたいという気持ちになってスタートした。4年前の自分に何か言うとしたら『そこで諦めるな』って多分言いますね」。
結婚と出産、子どもを保育園に預けて仕事と家事をこなす。その切り替えが練習の集中力につながっている。「カーリングの時間と育児の時間。メリハリをつけて生活をしている分、競技に生きているなと思う」と4年前との違いを実感する。
選手最年長でオリンピック経験者の近江谷杏菜選手は「4年前に敗退した直後は、本当に何もなくなってしまった。そこから始まり、カーリングを続けるといっても、ただ始めるだけではなく、世界一をめざすという覚悟で始めたので、それに必要なこととか、物とか、人とか。それを追い求めてたくさんの人に支えていただいて。スポンサーさんやファンの方々も増えてきて、こんなに応援してもらえるチームって本当に幸せだなあって思う」とそんな気持ちで氷の上に立っていると語る。
吉村選手はまた「4年前ここ(稚内での代表決定戦)で負けて悔しい思いをして、そこからみんな強い覚悟を持って一からスタートし、周りの方々に支えていただき、再びここに立てていることを誇りに思う」と感謝。その上で「皆さんの応援の想いに自分達の強い覚悟を重ね、一投一投強い気持ちで投げられている」と〝魂の投球〟を語る。 <つづく>(寒)
連載 フォルティウス より強く 遠回りの道ここから ⑪
2025-12-05
スポーツ
再び崖っぷち
でも選手たちは意外と…意識せず

タイブレークを制したその日の午後、フォルティウスはSC軽井沢クラブとの決定戦1試合目に臨む。
予選での対戦を含め相手からトータル3勝をした方が優勝というルール。予選の成績は互いに1勝1敗。先にあと2勝したほうが優勝で、逆にあと2敗したチームが負け。その決定戦第1試合、フォルティウスはSC軽井沢クラブの前に3―11と大敗する。
トータルの対戦成績1勝2敗で、またまた後がなくなった。
優勝しなければ道が途絶える今年の日本選手権をはじめ、今回も予選2連敗からスタートし、一つも負けられない状況でここにきて尚、必勝しかない境遇にさらされる。
負けたら終わり。ここまで幾度となく崖っぷちを経験してきたフォルティウスだが、試合後に小野寺佳歩選手は「意外と崖っぷちという感じはしなかった」と本音。吉村紗也香選手も「負けたら終わりという中で、みんなしっかりと忍耐強くプレーできていた。技術もそうですけれど、メンタルの面でも強くなったなあと選手それぞれが感じていたと思います」と振り返る。
コーチボックスから試合を見つめた船山弓枝コーチは「予選2連敗から始まり、タイブレークや決定戦も負けられない試合が続きましたが、チームはこの4年間、新スポンサーやファン、家族に支えていただきながら、さまざまな試練を乗り越えて、力強く成長してきた経緯があった。だから『できる、必ず結果が出る』と信じて試合に臨むことができました」と、ここまでの道のりを知るチームの一員として、厳しくも優しく、氷上の4人に安心の視線を送り続けた。 <つづく>(寒)
出場2枠懸け、8カ国激突
フォルティウス 6日に対アメリカ
ミラノ・コルティナオリンピックカーリング競技(来年2月4日から)の出場権を争う、世界最終予選は6日、カナダ・ケロウナ市で開幕する。男女各2枠を懸けて激突する。
男女それぞれ8カ国代表チームが出場。このうち日本女子代表・フォルティウスは6日の初戦でいきなり、強敵アメリカと顔合わせ。以降も強豪ぞろいで手を抜けない。予選の成績上位3チームが決定戦に進出する。
予選リーグ対戦相手と試合開始日時(日本時間)は次の通り。
<予選リーグ>
【日本女子】
▽第1戦=アメリカ(6日午後零時)
▽第2戦=ドイツ(7日午前7時)
▽第3戦=オーストラリア(8日午前2時)
▽第4戦=チェコ(8日午後零時)
▽第5戦=トルコ(9日午前7時)
▽第6戦=エストニア(10日午前2時)
▽第7戦=ノルウェー(10日午後零時) (寒)
中学生「税についての作文」札幌国税局長賞受賞
2025-12-05
教育・文化
置戸中3年・尾崎カンナさん
「税の力は金メダル」

税をテーマに全国の中学生から募集した「中学生の『税についての作文』」(国税庁など主催)で、置戸中学校3年の尾崎カンナさんが札幌国税局長賞を受賞した。「しっかりとした立派な作文」だと、たたえられている。
スキーのアルペン競技を頑張る尾崎さん。中2の昨シーズンは全国中学校スキー大会の女子回転と大回転に出場したほか韓国で1月開催の第1回日韓中少年冬季スポーツ交流事業の日本代表(全国で8人)に選抜された。
「税の力は金メダル」と題した作文は「物騒な世の中でもオリンピックの開催中は明るいニュースが日々舞い込み、元気が出る映像や温かい言葉が次々とあふれだす」で始まり「しかし、成績を残せなかった選手に対しては『税金泥棒』などと批判的な言葉をぶつける人もいる」と最近の風潮に疑問符を投げかける。
振り返って自分に当てはめると「初めての海外派遣だったが、遠征費の自己負担がほとんどなかったことに驚いた」と続け「国や関係団体の支援により、貴重な経験をさせてもらった」と感謝する。
その上で「私たちにできることは、選手にプレッシャーをかけることではなく、がんばってきてくれ!と税金で経験を積ませることである」とまとめる。
表彰状を受けとり、尾崎さんは「税がテーマだったけれど、よくわからないことが多かった。でも自分の好きなものにあてはめることで少し近くなった」と出稿当初にふれ、書き終えて「納税することで、夢が叶うことを知ることができた」と自分の成長を語る。
作文の最後は「私はそんな税の力に金メダル以上の価値があると思っている。」と結んでいる。 (寒)
全日本U12サッカー選手権でレフェリング
2025-12-04
スポーツ
北見柏陽の鈴木さんと北見北斗の高久さん
ユース審判員として道サッカー協会が派遣
いざっ全国へ

北見柏陽高校3年の鈴木陽和(ひより)さんと北見北斗高校1年の高久誠弘(まさひろ)さんは、26日から鹿児島県で開かれる全日本U12サッカー選手権大会にユース審判員として出場する。
同選手権のユース審判員は全国の都道府県から32人が選出され、北海道サッカー協会からはオホーツク地区の2人が選ばれた。
2人とも中学時代に4級審判員となり、高校1年で3級に合格。鈴木さんは昨年に続き同選手権で笛を吹くことになった。
初選出の高久さんは「全国大会でしかできないことを経験したい。緊張しますが、大会の成功に少しでも貢献できるよう、力を発揮したい」。鈴木さんは「日本一を決める大会なので、緊張感が違いますね。昨年はプレッシャーでうまくできなかったことに再挑戦したい。自信を持ってジャッジし、選手達をしっかりサポートしたい。楽しみです」と話す。
高久さんは現在、サッカー部で選手として活動。少年団時代にコーチのレフェリングを見て審判員に憧れを抱いたという。今後も選手を続けながら2級、そして「将来は1級を」と語る。鈴木さんとは道サッカー協会の研修会で出会い「色々と教えていただきました」。
鈴木さんはすでにサッカー部を引退しており、高校卒業後はクラブチームで選手を続けながら2級審判員合格を目指す。 (柏)
北見赤十字病院でモルック体験会
2025-12-04
スポーツ
フィンランド発祥・軽スポーツの魅力に触れる
大空町の松本さんが紹介
頭の体操にも

フィンランド発祥の軽スポーツ、モルックの体験会が11月29日、北見赤十字病院で開かれた。同病院の患者やスタッフ、一般市民ら30人ほどがモルックの楽しさに触れた。
モルックは木の棒を使って行うボウリングに似た競技。手持ちの棒(モルック)を投げて地面に立てた12本のピン(キットル)を倒し、得点を競う。
大空町が体験会に協力し、町教委の社会教育主事で昨年函館市で開かれたモルック世界大会に出場した松本晃さんが講師を務めた。同町は今年、大空町モルック協会を設立するなど競技の普及拡大に力を入れている。
松本さんはモルックの魅力やルールを説明し、同病院の和田侑也内科医師は「認知症予防やリハビリにもつながります」と紹介した。
参加者は早速、チームに分かれて対戦。一度にたくさんのピンを倒す爽快感や狙ったピンに当てる達成感を味わいながら、モルックの魅力に引き込まれていた。
小学1年生の子どもと参加した40歳の男性は「初めて会う人達と一緒に盛り上がることができました。手軽にできて(得点の計算で)少し頭を使うので、子どもから大人まで楽しめますね」と話していた。 (柏)
連載 フォルティウス より強く 遠回りの道ここから ⑩
2025-12-04
スポーツ
優勝するしかない日本選手権を制覇
代表決定予選は連敗の崖っぷちスタート

チームは高みをめざし、海外にも活動の場を広げる。カーリングの世界最高峰とも言われるグランドスラムなどの国際大会で腕を磨いた。その成果が日本選手権で現れ、2021年に制覇する。
一方、26年のミラノ・コルティナダンペッツォオリンピック女子カーリング日本代表チームを決めるための代表決定戦は、出場するためのいくつかの規則が設けられた。
24年に日本選手権を制したSC軽井沢クラブが真っ先に決定戦入り。25年の日本選手権開催時で世界ランク国内上位のロコ・ソラーレ(当時世界5位)は日本選手権3位に入れば決定戦に進出。当時世界ランク11位のフォルティウスは25年の日本選手権で優勝するしか、ミラノはもちろん世界最終予選に進む道がなくなった。その崖っぷちの日本選手権でフォルティウスは優勝する。
女子カーリングの世界最終予選日本代表決定戦は9月、稚内市にSC軽井沢クラブ、ロコ・ソラーレ、フォルティウスの3チームを集め開催。予選で各チーム2戦ずつ戦い、上位2チームが決定戦に進む。その予選リーグでフォルティウスは初戦、ロコ・ソラーレに7―9、2戦目はSC軽井沢クラブに6―8で連敗。一つも負けられない崖っぷちにまたもや立たされた。
予選2日目。勝利しなければ道が途切れるフォルティウスはロコ・ソラーレに7―6、ここも勝つしかないSC軽井沢クラブに5―3で勝利した。その結果、3チームが2勝2敗で並び、ロコ・ソラーレとのタイブレークに。勢いに勝るフォルティウスが7―2と圧倒し、SC軽井沢クラブとの決定戦に進む。 <つづく>(寒)
連載 フォルティウス より強く 遠回りの道ここから ⑨
2025-12-03
スポーツ
近江谷、小野寺、吉村の3選手 初めて一つのチームに
2014年

近江谷杏菜選手はチーム青森の一員として、バンクーバーオリンピックへの日本代表チーム決定戦に勝ち、2010年バンクーバーオリンピックに出場した。
代表決定戦で敗れ、2010年4月に中京大に進んだ小野寺佳歩選手は、盟友・吉田知那美選手の誘いでカーリングを復活。2011年4月、新チームの北海道銀行フォルティウス発足と同時に加入した。再び吉田選手とチームメートになる。
北海道銀行フォルティウスは2013年9月のソチオリンピック日本代表決定戦で勝利。14年2月のソチオリンピックに小笠原歩さん、船山弓枝さん、小野寺選手、吉田選手、苫米地美智子選手で出場。ところが小野寺選手はオリンピック初日に現地でインフルエンザに罹り、リザーブでの参加となる。チームは5位だった。
2013年のソチオリンピック日本代表決定戦で4位敗退した吉村紗也香選手は翌14年、五輪後の再出発を図る北海道銀行フォルティウスに近江谷選手とともに加わる。ここからはスポンサーやチーム名が替わっても吉村、近江谷、小野寺の3選手はその後11年間、一緒に戦ってきた。
小笠原歩選手の18年の退団で抜けた新たなスキップを決めるときも近江谷、小野寺両選手は「吉村さんにやってほしい。吉村さんしかいない」と仲良く一致。みんなでスポンサー探しに奔走した。
吉村選手をスキップに小野寺選手、近江谷選手に現・コーチの船山弓枝選手の体制が固まった2018~19年シーズンからは安定した成績を残す。とは言っても北海道選手権は勝てるが日本選手権では3位の連続。強いけれど今一つ突き抜けることができず「私達、遅咲きだから」と自分達でレッテルを張っていた。 <つづく>(寒)
町民モルック大会…
2025-12-03
スポーツ
訓子府で初開催
高校生から90代まで 体力や年齢越えて交流

訓子府町で初めての町民モルック大会が11月30日、町屋内ゲートボール場で開かれた。高校生から90代まで22チーム、80人余りが参加し、競技を通じて体力や年齢を越えた交流が生まれた。
誰でも気軽に楽しめるフィンランド発祥のモルックを通して、体力づくりや異年齢交流を広げようと、地域おこし協力隊の小見飛翔隊員が企画した。大会前にはモルックサークルの立ち上げをサポートしたり、ゲートボール場の夜間開放を行いながら初心者向けにレクチャーを行うなど、競技のすそ野を広げた。
大会には訓子府高校の軽スポーツ部や老人クラブ、地域おこし協力隊、趣味仲間などで構成するさまざまなチームが参加。4ブロックごとにリーグ戦を行い、1位通過した4チームで決勝トーナメントを行った。
大会最高齢はチーム「ケアハウス」として出場した星賀譲さん、佐藤昌文さん、中山景子さんの3人。全員が92歳で、10月の体験会をきっかけにモルックを始めたばかりというが、高校生チームとも互角にプレーし、年齢に関係なく楽しめるモルックの魅力を体現していた(写真)。
参加者達は「みんなでにぎやかに楽しむ雰囲気がいい」「緊張したけど仲間と一緒に楽しめた」などと笑顔で話していた。大会は町内の70代夫婦らでつくる「豊坂」が優勝した。
北見地区ママさんバレーボール連盟が…
2025-12-03
スポーツ
幅広い世代で50周年
記念の紅白試合は終始笑顔あふれる

北見地区ママさんバレーボール連盟(加賀静枝会長)の創立50周年を記念する紅白試合が11月30日、北見市内のサントライ北見で開かれた。
既婚女性の9人制バレーボールチームで組織する同連盟は1975(昭和50)年に設立。年2回の連盟主催大会をはじめ全道や道北、道東大会の予選、研修会などが行われている。最盛期には31チームが加盟したが、現在は12チームとなり、20代から80代まで幅広い世代の女性達が生涯スポーツとして活動している。
紅白試合には12チームから約100人が参加。所属団体の垣根を超えて抽選でチーム分けを行い、50歳以上のシニア、49歳以下のミドル各4チームごとに対戦した。ゲームの途中、サイコロを投げて出た目の指示に従う特別ルールもあり、会場は終始笑顔と歓声にあふれていた。
この日は懇親会とバザーも開催。バザー会場には野菜や会員手作りの雑貨などが並び、益金は連盟の活動費のほか一部は被災地の義援金に役立てられる。
加賀会長は「これまでの歩みを忘れることなく、今後につなげていきたい」と話していた。
問い合わせは同連盟事務局の辻百合香さん(090-8901-3849)へ。
弓道、選抜大会へ闘志
2025-12-01
スポーツ
北見商業高2年・木内 遥琉さん
北見商業高校弓道部の木内遥琉さん(2年)が、第47回北海道高校弓道選抜大会北北海道大会(10月、旭川市)の個人男子の部で1位になり、12月23日から静岡県で開催される第44回全国高校弓道選抜大会に出場する。「ここまで育ててくれたみなさんに感謝して、いい結果を報告したい」と静かな闘志を燃やしている。
昨年の雪辱果たし北北海道No.1に
いざっ全国へ

昨年の同大会地区予選では決勝で惜しくも敗れ、北北海道大会出場は叶わなかった。「すごく悔しかった。次は絶対に上にいきたいと思いました」。練習に励んで臨んだ今年の地区予選。決勝で見事上位に入り、北北海道大会進出を決めた。
北北海道大会の予選は8射を2回に分けて行い、5中以上で決勝に進む。前半は2中だった木内さん。気持ちを落ち着けて挑んだ後半に3中し、決勝に進んだ。
決勝は、10人が1人1射ずつ打ち、的中した人のみが残っていく「射詰め」。「射詰めは得意。いつも通り引くことができました」との言葉通り、5射連続で的中させ1位で全国を決めた。「今までやってきた練習の成果が出せた。これまでやってきたことは間違いではなかったと思えて、うれしかったです」と笑顔をみせる。
木内さんが弓道を始めたのは高校から。「中学校の先輩が高校で弓道部に入っていて、かっこいいなと思いました」。現在は1、2年生18人の同部主将を務める。「オホーツクはレベルが高く、恵まれた環境にあると思うし、自分のやりたいように練習をさせてくれる部員のみんなにも感謝しています」と笑顔をみせる。
全国大会に向け「いっぱい引いて、体の使い方などを研究、勉強したい。1位を狙いたい」と話している。 (菊)
軽スポーツでイキイキ人生
2025-11-28
スポーツ
網走市健康推進協がモルック大会

健康づくりに関心を持ってもらおうと、網走市健康推進員協議会(山根伸一会長)は、市総合体育館で軽スポーツ「モルック」に親しむ大会を開いた。
モルックはフィンランド発祥のボウリングに似たスポーツで、年齢を問わずに気軽に楽しめる。健康づくりに役立つことから、同協議会は競技セットを4セット購入するなどして、市内での普及に力を入れる。
昨年に続き2回目となった大会には、16チーム(1チーム2人編成)が参加。予選リーグを経て、上位4チームが決勝トーナメントに進み順位を競った。
山根会長は「市民目線で健康づくりを推進している。モルックなどを通じて、市民の健康意識を高めていきたい」と話していた。 (大)
全日本マスボクシング選手権…
2025-11-28
スポーツ
里見直美さんが連覇
北見ボクシングクラブで腕磨く
北見ボクシングクラブの里見直美さん(57)は、11月3日に岐阜県で開かれた第5回全日本マスボクシング選手権大会のシニアU60(50~59歳)女子の部160㌢超で優勝した。里見さんは同大会に5回出場し、2年連続4度目の頂点に輝いた。
シニア女子の部で 来年は3連覇狙う

マスボクシングはパンチを当てずに寸止めで戦う「非接触型」のボクシング。試合では、有効打と見なされるパンチ数などで勝敗を競う。
里見さんは2021年から同大会に出場。21、22年は出場選手が少なく〝認定〟の形で優勝。23年の大会は3位となり、悔しさをバネにより一層練習に打ち込んだ。昨年は強敵を倒して正真正銘のチャンピオンとなり、連覇をかけて今大会に臨んだ。
里見さんは準決勝では青森県の選手を5-0、決勝は愛知県の選手を5-0で破り、再び全国の頂点に立った。
自身の戦いぶりについて里見さんは「準決勝、決勝ともなぜか動きが固くなってしまいましたが、勝ててホッとしています。コーチは、練習してきた左ボディをうまく使えたと言ってくれました」と笑顔を見せる。
来年の全国大会は札幌で開催予定。「ぜひ勝ちたい。今年の経験を糧に頑張ります」と3連覇を見据えている。 (柏)
ビクトリーは生活のほとんど
2025-11-27
スポーツ
団活動振り返り、周囲に感謝

祝賀会でスポットライトを浴びながら入場した白幡さん(写真)は、出席者に深々と頭を下げながら席に着いた。少年団活動を振り返り「あっという間の50年。いろんな方々に助けていただいた。関わってくださった皆さんのおかげ」と感謝が尽きない。
甥っ子へ野球を教えているうちに、野球をやりたい子が自然と集まり、ならばと1975年にチームを発足。翌年には北見市野球連盟少年部に加盟し、公式戦に出場するようになった。
発足当初は父母の会もなく、団員達のユニフォームはポケットマネーでそろえた。試合数は今ほど多くなく、夏休みには団員達とキャンプをし、野球以外でも楽しんだ。プライベートでは78年に美恵子さんと結婚し、その翌年、長女が誕生した。試合のスコアラーをしていた美恵子さんに代わり、団員の母親がグラウンドで長女の子守りをしてくれたことも思い出だ。
選手達がいいプレーをした時は「100点!!」「ナイスプレー!」とたくさん褒める。「子ども達に気持ちよく、伸び伸びとプレーをしてもらたい」。そんな気持ちで昔から続けている。
若いころは、熱くなりすぎて団員達を感情的に怒ることもしばしば。それでも「あれだけ怒られていた子ども達が卒団した後も野球を続けてくれていることが嬉しい」と進学先での活躍を耳にするたび喜びが込み上げる。
かつての団員が父親となり、親子2代でビクトリーの一員としてプレーする姿に月日の流れの早さを感じる。白幡さんにとってビクトリーは「生活のほとんど」。チームの夢の実現に向け、今後もサポートを続けていく。 (理)
北見の野球少年団ビクトリーが創立50周年
2025-11-27
スポーツ
半世紀分の感謝伝える記念式典
白幡代表 立ち上げから現在まで指導続け

北見南小学校の児童で構成する野球少年団「北見ビクトリー」の創立50周年記念式典が22日、市内のホテルで開かれた。現役団員をはじめ卒団生や歴代父母ら110人あまりが出席し、1975年のチーム立ち上げから半世紀にわたり少年団活動を支える白幡隆代表(72)へ感謝を伝え、心温まる節目の1日とした。
乾杯の挨拶に立った竹村文宏監督は「50年という長い歴史を刻んでこられたのは何よりも白幡さんの存在があったから」と感謝を述べ、「今日までグラウンドに立ち続け、子ども達に情熱を注ぎ、指導者や保護者を温かく見守ってくださった。その姿勢に、ただただ頭が下がる思いです」と、存在の大きさに触れた。
加藤耕太郎キャプテンは「白幡さんはいつもたくさんほめてくれる優しい人です。これからもたくさんのことを教えてください」とメッセージを送った。
記念品の贈呈では、白幡さんの孫で同団OBの荒川壮大さんが登壇。団からの50年分の感謝の気持ちとして白幡さんにゴールデングローブを、妻の美恵子さんにプリザーブドフラワーを手渡した。
白幡さんは「言葉にならないほどうれしい。入団してくれた子ども達と団員を支えてくれた父母の会の皆さま、たくさんの指導者のおかげです。素晴らしいビクトリーの子ども達のためにもう少しだけ野球を続けさせてもらいたい。今後ともよろしくお願いします」と挨拶した。 (理)

