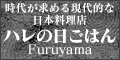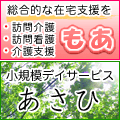国道39号線沿いの本町1丁目バス停付近に、高さ130㌢ほどの石門がある。「石北大通、歩行者専用道」の看板が目につく。ここが石北大通の東端となる(写真①)。
一歩足を踏み入れると、右側に緑色、左側に赤色の小道が西へ伸びている。老朽化は進んでいるものの、緑の小道には自転車の絵が、赤の小道には手をつなぐ大人と子どもの絵が描かれている(同②)。(この緑と赤の小道は、途中で何度か左右が入れ替わる)
鳥のさえずりとともに歩みを進めると、北2条通りに出る。左手を見ると「屯田歩兵第四大隊本部之跡」の石碑が見える(同③)。1926(大正15)年7月17日に、北見市によって建立されたものだそう。
北2条通りを渡りさらに進むと、赤い小道は広くなり、通りの真ん中に堂々とハルニレの木がそびえ立っている(同④)。
北3条通りを渡り終えると、今度はプンゲンストウヒの木が出迎える。時折「ガタン、ガタン」と鳴り響き、地下に列車が走っていることを思い出させる。
北4条通りを過ぎると、赤い小道と緑の小道の間が広くなり、たくさんの樹木が植えられている。なかでも中央にそびえ立つニセアカシアは圧巻だ(同⑤)。
緑園通りを越え、しばらく行くとダスト広場が見えてくる(同⑥)。そこには噴水も設置されているが、今年から水施設の稼働は休止との看板が―。
とん田通りを過ぎると、右手にSL広場がある。昭和の時代に活躍した、C58とD51の蒸気機関車と、DB21の貨車移動機が展示されている(同⑦)。
高栄通りで赤と緑の小道は終了。そこからは1本の小道になる。少し行くと右手に北見トンネルが見え、時折、列車が姿を現す(同⑧)。1本の小道はそのまま真っ直ぐ続き、小町川で終わる。ここが西端だ。写真⑨はその手前の高架下。
全長約2・3㌔の道のりには、高木36種類、1500本あまり、低木18種類、1万6600株あまりが植えられており、災害時の避難所にも指定されている。
風の心地よさや鳥のさえずりを感じながら、頭を空っぽにしてのんびり歩くと、日々の雑踏から自由になれる。石北大通なら、そんな時間を作れそうだ。 (知)