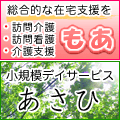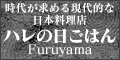■「指定」じゃない
市役所・新庁舎は、中心市街地にあった旧金一舘ビル周辺跡地に建設。津波被害などを懸念し、高台への建設を望む声は少なくなかったが、水谷洋一市長は「中心市街地の活性化にも期待できる」として決断した。
7月30日の津波注意報は新庁舎完成後、初めてのことだった。本紙は改めて、新庁舎の避難所機能を調べてみた。
新庁舎は、市の防災拠点施設との位置付け。5階の議場は避難所になるが、市で指定する「緊急避難所」や「一時避難所」とは性質が少し異なる。
5階議場は、「一時避難スペース」(約260人収容可能)で、避難所ではないようだ。「あくまで一時避難する場所。基本的には指定の避難所を利用してもらう」(市の担当者)。
一時避難スペースとなる議場には議員ら用の机があり、ボルトで固定される。万が一の際、この机はどのように移動するか? 市の見立ては「職員が手作業でボルトを外し、机を移動させる。作業は30分ほどで完了すると思う」だ。
■期待する市民
水谷市長の肝入り事業としてスタートした防災ラジオ。基本的に市民なら誰でも無料で借りられる。
7月30日の津波注意報の際は、地元FMラジオ局が市の要望に応じて不定期に「海岸に近づかないで」などと呼びかけた。
70代の男性市民は「NHKラジオ・テレビのほうが詳細な情報を流していた。防災ラジオは網走市民が知りたい情報を流してくれると思っていたが、期待外れだった」と話していた。
防災ラジオの貸与は2019(令和元)年度にスタート。市は約7200万円を投じ、ラジオは7千台用意した。
当初の貸与対象は「75歳以上の高齢世帯」などとしていた。しかし、貸与数が増えないことから、前年度から対象条件を緩和。昨年11月からは、年齢制限と対象区域を撤廃したものの、いまだに2千台ほどのラジオが倉庫に眠っている。