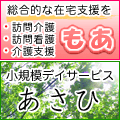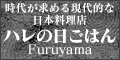第1部で谷口暁星氏 新しい観測装置を紹介
第1部では同大学情報通信系特任助教の谷口暁星(あきお)氏が「138億年の宇宙の歴史の最初の数十億年で、星や銀河がどのように作られたのかという問題は、現在も完全に解明されていない」として解明の鍵となる、時間×空間の3次元広域観測とこれを実現するために同氏らが関わる新しい観測装置DESHIMA(デシマ)やTIFUUN(タイフーン)を紹介した。
電波から可視光、γ線まで「様々な波長で星やその材料となるガス、ダストを調べることが重要」とし、同氏ら日本とオランダが共同開発した装置科学に宇宙科学、データ科学を組み合わせ3次元観測に挑んでいるとした。
同氏はまた「本学には多くの宇宙理学研究者が在籍し、天文学演習、現代天文学など多彩な専門科目がある」として「天文学を学んでソフトウェアやシステム開発業界で活躍する人材もいる。宇宙理学を学びデータサイエンティスト、AIエンジニアをめざしませんか」とPRも忘れなかった。
第2部で升井洋志氏 元素の話わかりやすく
解明にアプローチの重要さ説く
第2部は同大学情報通信系教授で情報処理センターの升井洋志センター長が「宇宙の始まりと素粒子・原子核」という難しい話に「ものすごく大きい世界と小さい世界」というサブテーマを加え、できるだけ分かりやすく講義した。
日本人で初めてノーベル賞を受賞した湯川秀樹氏の中間子理論を例に、存在する4つの基本的な相互作用(ちから)のうち、電磁気力と重力以外の「強い力」と「弱い力」についての説明から導入。
太陽など恒星内部で合成されるのはせいぜいFe(鉄)の重さの元素までだが、鉄より重い金や銀などの元素が地球にあるのは「超新星爆発(ビッグバン)で、ものすごい勢いで爆発した力により地球に降り注いだことによるもの。すごく不思議な話だ」と大きな出来事と小さな世界の関係性に興味を抱かせた。
中性子のβ崩壊でエネルギー変化のつじつまが合わないことから科学者は「マイナスの存在を作ってしまえばいいと考えた」そう。未解決問題の解明について升井氏は「データサイエンスでは、物の見方の入口は何が特徴かを見つけることから始まる」とアプローチの重要さを説いた。
升井氏が理化学研究所に在籍していた際に見つかって話題になった新元素Nh(ニホニウム)の命名の由来についても語った。