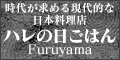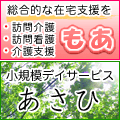紙面を発行してきた置戸タイムス社の田村昌文社長(76)、山本勲前社長(82)、北山雅俊編集長(71)、佐久間光昭編集委員(75)の4人を迎え、馬場さんが聞き手を務めた。
休刊について田村社長は「75年まで続けたいという思いはあった」と明かすも、発行部数はこの30年余りで約550部減少し、会社の財政面や社員の高齢化、新たな人材確保の点から「苦渋の決断だった」と述懐した。
昨年12月31日発行の最終号は次代を担う若者達を紹介した。特集を組むにあたり、北山編集長は「タイムスは辞めるけど置戸の営みは続いていく。そこには若い人達が頑張っているという姿をお届けしたいと思った」と語り、佐久間委員は「最終号が出来た時はさみしかった。これが最後かと紙面を見てグッときた」と振り返った。
タイムスが地域で果たしてきた役割について「貴重なまちの365日24時間を活字に残すことができ、置戸にとって大事な財産になったのではないか」と田村社長。
参加者からは〝タイムス愛〟が語られ、置戸出身で現在は北見在住の長谷川仁美さんは「置戸を離れてタイムスの見方が変わった。紙面の温かさや写真の奥に込められた物語が感じられる、代えがたいものでした。タイムスが伝えてきた温かな思いをこれからどうするのか、一人ひとりが考えて行動できるといい」。十数年前に置戸に移住してきた荒谷陽子さんは「町とのつながりをくれる大きな存在で、新聞というものを身近に感じることができました。本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
参加者の声を受け、田村社長は「タイムスは町民をつなぐ接着剤だった」とあらためて地域で果たしてきた役割に触れ、「紙面はなくなっても別の動きが出てくると信じていますし、期待しています」と地域にエールを送った。イベントの最後には「73年で終わらせることになり申し訳ありません。本当にありがとうございました」と深々と頭を下げた。
置戸タイムス社は今月31日の解散にあたり同日、町に150万円を寄付した。人材育成基金など3基金に積み立てられる。 (理)