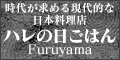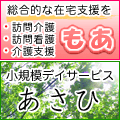北登蒸留施設は1967年、ハッカの蒸留施設として建設された。現在はハッカに代わってシソの蒸留に使用されており、今年は10月23日~11月2日にかけて蒸留作業が行われた。
JAきたみらい管内では香料用の青シソを市端野町北登、二区、川向の農家7戸でつくる端野町シソ耕作組合が11㌶で作付け。5月上旬ごろに種をまき、9月上旬から中旬にかけて収穫・はさ掛け(乾燥)を行い、10月下旬から蒸留作業に入る。香料用青シソは手間のかかる作業が多く、生産者は減少しているが高収益作物としての期待も高まっている。
施設内には直径3㍍、深さ4㍍ほどの蒸留釜が3基並ぶ。ハッカ蒸留と同様、乾燥させた青シソを釜に詰め、高温の蒸気を通すと香り成分を含んだ蒸気となる。これを冷やすことで水と油が分離され、比重の違いによって油が抽出できる仕組みだ。
3基の釜がフル稼働
10月31日は平川千春さん(60)方が蒸留作業を実施。午前7時から午後4時ごろまで3基の釜をフル稼働させ、全15回の蒸し作業を行った。釜の中に乾燥した青シソを敷き詰めるように入れていくと、あたりに粉塵が舞い、慌ただしさが加速する。青シソに蒸気が効率的にあたるよう、6~7人が釜の中で一斉にジャンプをして踏みならす。それを数回繰り返し、釜いっぱいにする。
肌寒い季節に行われる晩秋の作業。釜に乾草を詰め、次の蒸留に控えて乾草を用意し、そうしている間に別の釜の蒸留が終わり、また乾草を入れる―。作業にあたる人達は切れまなく続く作業に「汗が止まらない」「寒さを感じる暇はない」と言う。
蒸すこと1時間半。釜の蓋が開けられると湯気が一気に広がる。蒸し終えた青シソの塊がワイヤーで持ち上げられ、トラックの荷台へと運ばれていくさまは圧巻の光景だ。平川さん方では蒸し終えた青シソを堆肥化して利用するという。
高温小雨、今年の出来は「まずまず」
抽出された油は淡い黄金色よりもやや緑がかって見えた。水が混じらぬように手作業で一斗缶へと注ぎ、ろ過作業を経て出荷される。組合全体では例年だと約380㌔の油が採取できるそうで、平川さんは「今年は雨が少なく、暑かったが、それが適度な刺激となったのか生育はよく、油の出方もまずまず」と手応えを語った。
シソ油は香料の原料として出荷されており、私達が日ごろ何気なく口にしている食品の香りづけに、きたみらいのシソ油が使われているかもしれません。 (理)