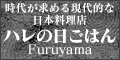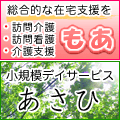もし自分が認知症と診断されたら、「これからどうなるのだろう」「周りに迷惑をかけてしまうかもしれない」と、不安に陥るかもしれない。しかし、隠さず公表し、周りの協力を得ることが大切だ。「今や65歳の5人に1人、国民の17人に1人が認知症と推計される時代。糖尿病や高血圧と同じように、誰にでも起こり得ること。『自分もなるかもしれない』という認識を持ち、認知症の人やその家族が孤独にならないよう、地域の理解や支えが必要」と語る。
たとえ理解できない言動があっても、本人にとっては理由がある。頭ごなしに「おかしい、ダメ」と否定するのではなく、「行動には意味がある」と意識し「どうした?何かあった?」と観察する姿勢が大切だという。
また、認知症の人には記憶障害があるため「さっきのことは忘れている」ということも念頭において接する必要がある。「さっき言ったでしょ」「さっき食べたでしょ」と指摘されると、不安を強めるだけでなく、自尊心を傷つける恐れがある。
「家族もストレスをためないよう、周りに相談したり、デイサービスやショートステイなどを利用して、抱え込まないようにしてほしい」と呼びかける。
認知症の治療薬としては飲み薬と点滴があるが、どちらも完治するわけではなく、進行を遅らせるのが目的だ。点滴の場合は定期的に通院が必要となるため、「治療費や通院の負担と効果のバランスを考え、よく話し合って決めてほしい」と話す。また、「元々お出かけが好きな方が治療のために制限され、それがストレスになるのも望ましくない」とも指摘する。
「もし認知症に…」だれもが可能性
以前は認知症になると、何を言っても理解できなくなるという誤った認識から、本人抜きで家族と病院で決めてしまうことが多かった。しかし「認知症基本法」が制定され、本人のやりたいことを応援し、本人主体で進めることが法律で定められている。
早期発見、早期対応のメリットを聞いたところ、治療や生活習慣の改善などによって進行を遅らせることができるほか、次のようなことも教えてくれた。
【財産管理など自分で選択できる】ゆっくりと進行するため、住んでいる家はどうするか、お金が下ろせなくなったら誰にたのむか、延命治療はしたいかなど、自分の意思を家族に伝えられる。
【生活や人生の選択を自分で決められる】いつまで家にいて、最期はどこで迎えたいのかなども自分で決められる。
「残された家族が悩まずに済むよう、自分の意思を伝えることも大切」と述べる。
認知症の診断を受けた本人が、前向きな生き方や希望を発信する「希望大使(認知症本人大使)」として活躍する人たちがいる。同センターでは、ほっかいどう希望大使の松本健太郎さんの講座を11月1日(土)午後1時半から北見芸術文化ホールで開催予定だ。(知)